はじめに
管理人は社会人としてハード的なスキルを身につける自己研鑽はある程度完了したため,ソフト的なスタンスや思想哲学の裾野を広げたいと考えて「名著100本ノック」を開始しました。本書籍もその一環で読んだものになります。読書記録は下記のページでまとめています。
基本情報
| タイトル | 江副 浩正 |
|---|---|
| 著者 | 馬場 マコト/土屋 洋 |
| 出版社 | 日経BP |
| 発売日 | 2017年12月25日 |
| ページ数 | 496ページ |
概要と感想
この書籍『江副浩正』は,リクルート創業者である江副浩正の伝記であり,著者は元リクルート社員の馬場マコトと土屋洋である。あとがきによれば,馬場は「薫陶を受けた江副の功績と足跡を残す」ために,土屋は「江副から受けた恩義に報いる」ために執筆したとのことである。管理人は本書を読む直前に『リクルートのDNA —— 起業家精神とは何か』を読了しており,江副の掲げる思想やその背景はある程度把握しているつもりであった。しかし,本書を通じて自分がいかに江副のことを知らなかったのかという事実を思い知らされた。特に,リクルート事件の生々しい全容には圧倒され,江副の人物像について新たな発見が数多くあった。
江副浩正の二大功績
本書の最終章では,江副の功績は大きく二つに集約できると述べられている。それは「情報誌という媒体を創り出したこと」と「成長し続ける企業の思想と仕組みを創ったこと」である。前者は,従来カスタマー側(求職者や消費者)とクライアント側(企業や提供者)の間で十分な情報の透明性が確保されていなかった業界において,両者をつなぐ情報誌という新たな媒体を世に広めた功績である。例えば就職活動においては,学生は限られた企業情報しか得られず,就職のためには教授の推薦が必要という閉鎖的な採用慣行があり,企業側も幅広く自社を宣伝する手段を持っていなかった。しかし江副は,求人情報誌『企業への招待』を創刊し,続く『リクルートブック』へと発展させることで,この閉鎖的な情報環境をオープンに変革した。教授の縁故推薦に頼る採用を形骸化させ,学生と企業が直接出会える市場を作り上げたのである。まさに,民間企業のイノベーションによって雇用制度をあるべき姿に近づけた例と言える。
後者の功績は,「優秀な人材を採用し,その能力を全開させる組織を作ったこと」である。江副は「個」を尊重し,若い人材を次々と登用して新陳代謝を図る組織づくりを推進した。上から強制されて動くのではなく,社員一人ひとりが自ら目標を定め,自分のやり方で達成することを良しとする企業文化を築いたのである。これは現代で言うスタートアップ企業のフラットな組織文化にも通じる先進的なものであり,リクルートが成長を続け優秀な人材を輩出した原動力となった。
第一章:最期の瞬間から始まる物語
本書の第一章は少し意外な構成で,江副の晩年,最期の瞬間の情景から始まる。リクルート事件によって世間から隔絶されてしまった晩年の江副は,亡くなる当日まで株式投資に熱中し,自身がゼロから開発した岩手県の安比高原スキー場でスキーに興じる日々を過ごしていた。その日常はどことなく孤独でルーティン化しており,読んでいて寂しさが漂う。最期の朝,彼は安比高原の雪景色を眺めながらスキーを楽しみ,その数時間後に急逝する。この章の生々しい描写から,華やかな実業家であった江副が人生の最後に抱えていた孤独と影が強烈に浮かび上がってきた。
第二章〜第三章:幼少期からリクルート創業まで
第二章から第三章では,江副の幼少期から大学卒業後に「大学新聞広告社」(リクルートの前身)を設立するまでの軌跡が描かれている。大阪で生まれ育った江副の父親は数学教師であったが,非常に厳格な性格であり,女性関係にもだらしない一面があったという。この父との関係は江副の心に暗い影を落とし,「父親の呪縛からの解放」というテーマがのちに語られるほど,江副の原体験として彼を殻に閉じ込めてしまったようである。
幼少期,第二次世界大戦下での疎開や飢餓の体験も彼の人格形成に深く影響した。実際,本書によれば晩年に認知症が進行した際,東日本大震災の報道を見た江副は強迫観念に駆られ,保管場所も考えないまま米を3,000万円分も購入契約してしまったり,安比高原の芝生を剥がして芋畑を開墾したりする行動に出たとのことである。幼少期に飢餓状態で米軍兵士に「ギブミー・チョコレート」と懇願せざるを得なかった苦い記憶が,半世紀以上を経ても彼の中で生き続けていたのだろう。このような経緯で英語に対して苦手意識を持っていた江副は,ナチスの台頭から逃れて日本に来ていたドイツ人教師との出会いによりドイツ語を習得し,東京大学に現役合格した。
東大では,生活費を稼ぐために東京大学新聞の広告取りアルバイトを始めた。歩合制で給料が良かったこともあり精力的に働き,同時に下宿先の大和荘での友人・先輩たちとの交流によって,江副は次第に幼少期から閉じこもっていた殻を破りはじめた。この学生時代,彼は競技ダンスの愛好会にも所属し,女性との交流も増えていった。社交ダンスは晩年にオペラ事業へ関わる伏線にもなっている。東大卒業が近づくと,当時の仲間たちと共に「大学新聞広告社」を設立し,在学中に始めた広告業を発展させて起業への一歩を踏み出した。
第四章〜第六章:次々と生み出された新規事業
第四章から第六章では,リクルート(当時は日本リクルートセンター)が創業後に次々と新規事業の芽を生やしていく過程が描かれている。江副たちは資金繰りに苦労しながらも前払い制度など知恵を凝らして『企業への招待』を発刊した。これこそリクルートの原点となった求人情報誌であり,泥臭くも企業の採用担当に大声で売り込み営業をする江副の姿が印象的である。
また,この頃江副は父親から譲られた株式をきっかけに株式投資の魅力に気づき,ギャンブラー気質が芽生え始める。一方,求人情報誌に留まらず採用テストの開発にも手を広げた。企業と学生を結びつける情報誌だけでなく,企業側の採用プロセス自体にある「非効率」や「不公平」にメスを入れようとしたのである。江副が大学で第一志望ではなかった教育心理学を学んだことが功を奏し,東大心理の大学院生と組んで適性検査の研究・開発に取り組むことになった。当時開発した採用テストは従来の相場を大きく上回る高単価ながら市場に受け入れられ,現在も多くの企業で使われるSPI試験の原型を築いた。業務の効率化のためIBM製コンピュータもいち早く導入し,その中でエリート社員であった位田尚隆(後に江副の後任社長となる人物)との出会いも果たした。適性テスト事業はさらに企業向けの教育研修事業へと広がり,この頃にJDP研修(新入社員に対する自己変革研修)の基礎も整備された。リクルートの独自の人材育成プログラムであるJDP研修は,今でも新人研修の一環として受け継がれている伝統である。また,この時期にはドラッカーの教えを参考にして社是や社訓を整備していくプロセスも紹介されている(このあたりの詳しい内容は,先に読んだ『リクルートのDNA —— 起業家精神とは何か』に詳しく書かれていた)。
第七章〜第十章:不動産事業への拡大と試練
第七章から第十章では,リクルートが人材領域から不動産事業へと大きく事業領域を拡大していく様子が描かれている。高度成長期・バブル期のインフレ局面で不動産による含み益を経験した江副は,そのレバレッジ効果の虜になった。不況時のリスクヘッジにもなるとして不動産事業を伸ばすべく,鹿児島や岩手といった地方の過疎地を開拓してリゾートマンションを建設していった。特に岩手県の安比高原では新幹線開通も追い風となり,大規模スキーリゾート開発が大成功を収めた(安比高原は現在も多くのスキーヤーが集まるリゾート地である)。不動産開発を担う新会社「環境開発」(後にリクルートコスモスへ改称)も設立された。
さらに,求人誌と同じ発想で不動産業界向けの情報誌『住宅情報』も創刊した。住宅情報誌では特に女性の視点を重視すべきだと考え,江副は女性編集長を抜擢した。現場主義で徹底的に読者のニーズに寄り添った結果,この住宅情報誌も見事に成功を収めた。当時,リクルートのビジネスモデルを追随する競合も現れた。『企業への招待』にはダイヤモンド社,『住宅情報』には読売新聞社がそれぞれ競合誌を出してきた。しかし江副はこうしたライバルの出現を「変革のチャンス」と捉え,素早く大胆な人事異動や方針転換を行って次々と手を打った。競合の登場さえも成長の糧に変えてしまう柔軟さと決断力は見事である。
この時期に江副は父との死別を経験する。すると,呪縛から解き放たれたかのようにますます株式投資の世界に傾倒し,同時にそれまで持ち合わせていた謙虚さも失われていったと本書は指摘している。慎ましさを忘れて傲慢になっていく江副の姿は,前半の若き挑戦者の姿と対照的であり,特に印象に残っている。
第十一章〜第十五章:リクルート事件と江副の失脚
第十一章から第十五章では,リクルートコスモス(環境開発を改称した不動産会社)の未公開株譲渡に端を発したリクルート事件の発覚から江副逮捕,そして事件終焉までの経緯が生々しく描かれている。リクルートコスモスの店頭登録を巡って当初支援していた野村證券との調整が難航したため,江副は焦りから大和證券へと手続きを鞍替えした。しかし大和證券は「お世話になった有力者へ未公開株を譲渡するのは業界の通例で問題ない」という甘い認識で対応したため,政治家を含む多数の有力者への株譲渡が行われてしまった。のちに判明したことだが,もし野村證券の助言に従っていれば「たとえ通例でも政治家への未公開株譲渡は絶対にNG」という方針であったため,そもそも事件は起きなかった可能性もあった。結果論ではあるが,大和證券を選んだという判断がリクルート事件の引き金となってしまったのである。
これらの章では,江副の人に贈り物をしたがる性格が強調されている。印象的だったエピソードの一つに,ある合同竣工式で部下が用意していたサントリーのワインに代えて,江副が急遽「安比高原で採れたトウモロコシ」を来賓への手土産にするよう指示したというものがある。そんなサービス精神旺盛で面倒見の良い江副であったからこそ,上場直前に「これまでお世話になった方々」に自身の持つ未公開株をお裾分けしようと考えてしまったのだろう。彼はすでに譲渡済みの分も含め,自分の手持ち株をやりくりしながら多くの関係者と連絡を取り合い,株の分配に奔走した。しかしこの行為が贈収賄に当たるとみなされ,彼自身と政界・官界の要人を巻き込む一大スキャンダルに発展してしまった。
江副は不動産事業において,地方でマンション開発を進めるだけでなく東京に自社ビルを建設することにもこだわりを持っていた。西新橋ビルに始まり,G8ビル,G7ビルなど,現役世代でも名前を知っているリクルート関連のビルが次々登場するくだりには高揚感を覚えた。ちなみに2024年から2025年にかけてG8ビルの取り壊しが進められているが,江副が遺したシンボルの一つが消える決定は惜しいと感じる。
当時リクルートは多角化によって売上1,000億円規模の企業から1兆円企業へ急拡大しようと邁進し,社内では次々と新規事業が立ち上がった。LAN事業(オフィスの情報ネットワーク化)は時代を先取りしすぎて失敗したが,その最中に日米貿易摩擦の解消のため圧力を受けていたNTTを救うかたちで,江副はクレイ社のスーパーコンピュータ購入を二度も決断している。しかしこちらも事業としてはいずれも最終的に撤退を余儀なくされ,リクルート事件では批判の格好の材料にされてしまった。
こうした巨大企業への変貌を遂げる頃の江副は,前述のとおり謙虚さに欠け傲慢になっていた。本書の中でその変貌ぶりは「江副一号」と「江副二号」という対比で表現されている。印象的だった一節を引用する。
次々と新規事業を開設していった「江副一号」。それとは対照的に,「江副二号」は何一つ新しい事業を開発し,軌道に乗せられずに,リクルート王国の国王として君臨した。…「江副さんは…出された料理を,僕はこれが嫌いだからほかのものにしてよと代えさせた。」…ダンスの師…をパートナーに,江副の華麗なソシアルダンスの披露となった。…そしてあろうことか世界の並いるオペラ歌手を前に,江副はオペラ「椿姫」のアリア「乾杯の歌」を歌い始めた。小学生の歌唱で「可」をとって以来,高校のグリークラブでも音痴のあまりマネジャーに回された男が,ボイストレーナーについて血のにじむような努力を積んだ結果の歌声だった。だが,どんなに練習を重ねようと,謙虚さを身に付けた「江副一号」ならば,決して世界の巨匠の前では歌わなかっただろう。
「江副浩正」p.299-300より引用
度重なる取り調べや報道攻勢にさらされ,江副は心身ともに消耗していった。純粋な恩義からの贈り物がこのような結果を招いてしまったことに心が痛んだが,この感覚により,管理人は「江副浩正」が自分の中に住み始めたことを実感した。
第十六章〜:「リクルートイズム」
江副が去った後もリクルートが潰れずに済んだのは,残された社員たちがリクルートの独自の哲学を守り抜いたからである。
- 透明で中立的な開かれた経営でつねにあること
- 社員持株会をつねに筆頭株主とし「社員皆経営者主義」を貫くこと
- つねに組織の新陳代謝に努め,若いエネルギーに満ちた組織であり続けること
- 新規事業に果敢に取り組み,だれも手がけぬ事業をやる誇りをもち続けること
- つねに高い目標に挑戦し,その過程で個人と組織のもつ能力の最大化をめざすこと
- 徹底した顧客志向により,得意先の満足を最大化すること
- 個人を尊重し,社内はいっさいの肩書,学歴,年齢,性別から自由であること
この7つの独自性のうちどれか一つでも欠ければリクルートはリクルートでなくなる。そんな強い思想のもと,江副から社長を引き継いだ位田尚隆,続く河野栄子,柏木斉ら歴代経営陣の尽力により,リクルートはダイエー傘下からわずか数年で全ての負債を完済し,独立してみせた。さらに峰岸真澄の下で「グローバル展開と株式上場」を目標に掲げ,積極的なM&Aと海外進出を進めた。2014年にはついに株式上場を果たした。現在も成長を続けるリクルートグループがあるのは,先人たちがこのバトンをつないできたからこそであると本書を読んで強く実感した。
一方で,江副自身のその後の人生にも本書は触れている。事件後,公の場から姿を消した彼は,日本にオペラ文化を普及させるための「ラ・ヴォーチェ」事業を立ち上げた。そこには「リクルート事件で社会に迷惑をかけてしまった分を日本の文化振興で返したい」という思いが込められていたという。見る人によって晩年の江副の精力的な活動は「老害」に映ったかもしれない。しかし逆に,最期の瞬間まで動き続けようとする先鋭の事業家にも映る。
いったい何が年老いた彼をここまで駆り立て続けていたのか。にとって,その答えは最後まで分からなかった。皮肉にも,リクルートホールディングスの株式上場を目前にした2013年2月,江副浩正はこの世を去った。
リクルート事件とその学び
振り返ってみると,いわゆるリクルート事件は戦後最大級の汚職スキャンダルとして日本社会に大きな衝撃を与えた。この事件は日本の政治史にも大きな影響を及ぼし,政治資金規正法の改正や小選挙区比例代表制の導入など一連の政治改革の契機となった。実際,事件で竹下登首相が退陣し,自民党は1989年の参院選で結党以来初めて過半数割れとなる大敗を喫した。また,企業不祥事の面でも「未公開株による利益供与」という手口を世に知らしめ,今日の企業コンプライアンス体制構築の出発点になったといわれる。メディアによる権力監視の必要性や,市民社会が政治腐敗に目を光らせる大切さを世に示した事件でもあった。つまりリクルート事件には,単なる一企業の不正疑惑を超えた意義があったのである。
本書を読み終えて感じたのは,江副浩正という人物の光と影,そして孤独である。「天才は孤独である」という言葉があるが,本書では江副を「天才」と呼ぶ場面はほとんどない。それどころか,マスコミは彼を「素手でのし上がった男」と表現したという。実際,江副は誰もやったことのないことに果敢に挑戦し,その挑戦が社会に受け入れられるまで辛抱強く戦い抜いて,多くの事業を成功させ,社会を変えてきた起業家であった。ドラッカーの「経営とは社会に対する責任であり変革である」という趣旨の言葉を地で行くような,日本屈指のイノベーターであったと言える。その功績はリクルート事件によって一時かすんでしまったが,リクルートを中心に培われた人材輩出の文化や起業家精神は,その後も脈々と受け継がれている。
一方で,本書を通じて学んだのは謙虚さと倫理観の重要性である。江副は若き「江副一号」の時代には常に謙虚で,新しい価値を創造することに情熱を注いでいた。しかし成功を重ねるうちに「江副二号」とも言うべき傲慢さが生まれてしまった。その結果,自分では純粋な好意のつもりだった行動が周囲からは不正と見なされ,経営者生命を絶たれる悲劇を招いた。これはビジネスにおいてどんなに才能や実績があっても,謙虚さと倫理を欠けば一瞬で信頼を失いかねないことを教えてくれる。江副の栄光と挫折の物語は,現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれた。管理人自身,江副浩正という人物の功罪を深く知ったことで,「自ら機会を創り出し,機会によって自らを変えよ」というリクルートの社訓の重みを改めて噛み締めている。
おわりに
先に述べた一節の前段ではあるが,本書で最も印象的であった一節を自戒も込めて以下に引用する。
不動産やノンバンク事業に傾倒し,ニューメディア事業で疾走する江副のなりふり構わないワンマンぶりに対して,社内ではひそかにこう言い交わされ始めていた。
「江副二号」
敬愛の念を込めて「江副さん」と言っていた社員たちが,絶対君主のようにふるまう江副にとまどい,その変容ぶりを嘆くかのようにそう呼んだのである。…「謙虚であれ,己を殺して公につくせ」という葉隠精神…江副自身がその言葉を忘れた。…父の死,そして政府要職の座。これらが重なり,江副は少しずつ変容していった。もともと贈りものをすることに並外れた執着と心配りを示す江副だったが,それでも親しい人への贈答品は,たとえば安比高原のとうもろこしのようなものだった。それが,松坂牛「和田金」の最高級ひれ肉に,そして「吉兆」の三段重ねの豪華なおせち料理に変わっていった。政治献金を課税枠ぎりぎりまで際限なく増やしたので,パーティー会場では政治家たちがまず江副の席にあいさつに来た。
…取締役会は江副の独壇場になった。江副の成功体験に引きずられ,誰も反対意見を言い出せないまま,取締役会は江副の思い通りに動いていった。そしてリクルートは「誰もしていないことをする主義」からはほど遠い,デジタル回線,コンピュータレンタルの下請け事業,そして不動産業へと急激に傾斜していく。
次々と新規事業を開設していった「江副一号」。それとは対照的に,「江副二号」は何一つ新しい事業を開発し,軌道に乗せられずに,リクルート王国の国王として君臨した。

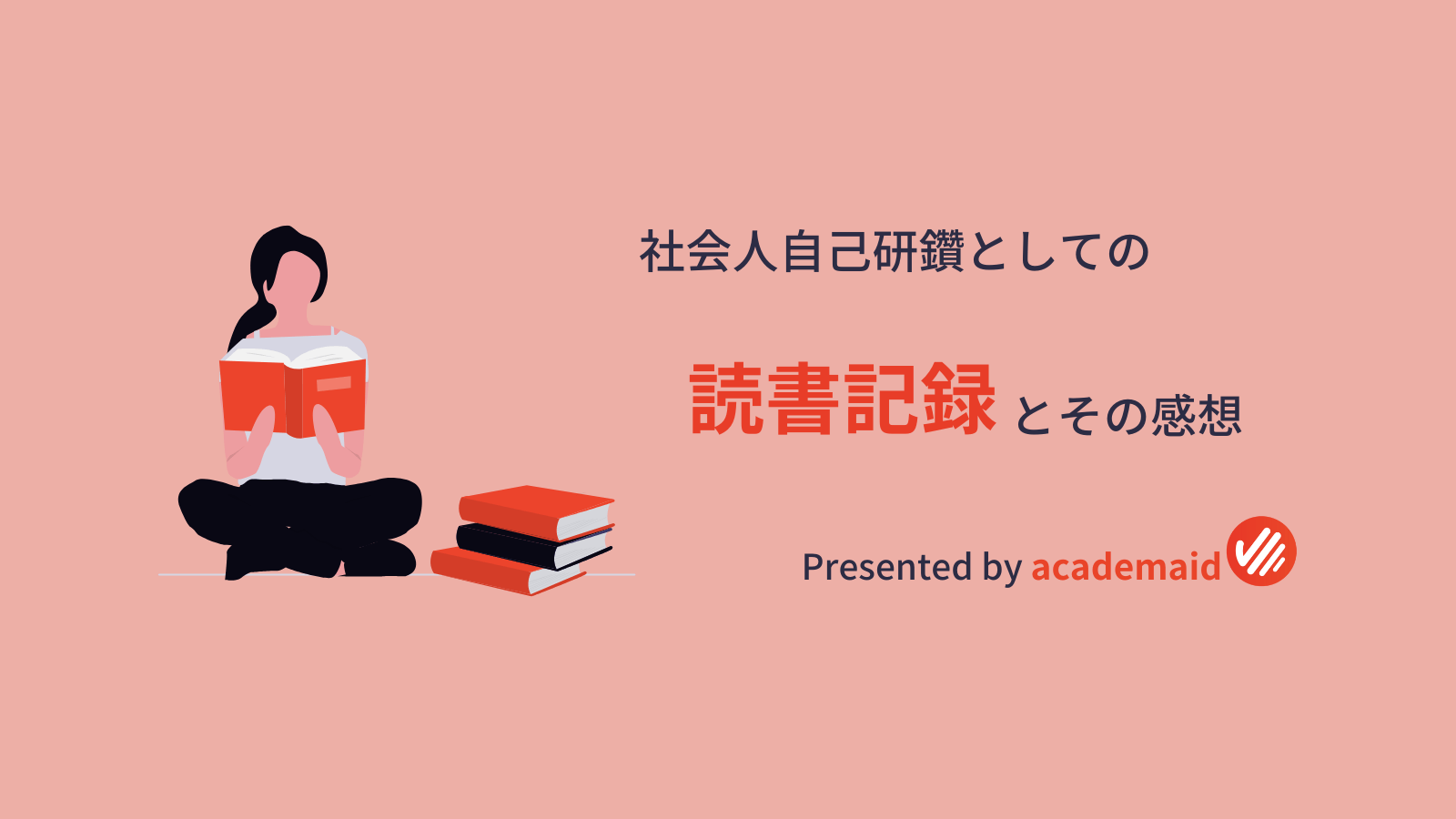


コメント