本稿ではIPA試験で必要とされる知識をまとめます。
午前II
PESTの覚え方
Politics・Economy・Society・Technologyと頭文字で覚えるしかない
ファイブフォースの覚え方
- 競合他社・新規参入者(の脅威)
- 代替品(の脅威)
- 買い手・売り手(の交渉力)
と分類して覚える。競合他社の脅威は「業者間の敵対関係」として図の真ん中に配置されることもある。
PPMの覚え方
第1象限〜第4象限まで半時計回りで問題児→花形→金のなる木→負け犬。問題児は成長率は高いが占有率がまだ低いことだけを押さえておけば,x軸は占有率を表して正の方向ほど占有率が低い,y軸は成長率を表していて正の方向ほど成長率が高いと理解することができる。
アマゾフの成長マトリクスとは
市場と製品の「新 or 既存」で4パターンに分類するやつくらいの理解度でOK
LBO・MBO・EBO・TOBの覚え方
まずBOはBuyoutなので買収のことを指す。そしてLBOのLはLeveragedであることを押さえればLBOが「どのように買収するのか」の手段を表すと理解でき,MBOのMはManagement,EBOのEはEmployeeであることを押さえればMBOとEBOが「誰が買収するのか」の形態を表すと理解できます。
TOBは完全に例外として覚えてしまうのがよく,原語のTake Over Bidで覚えるより「株式公開買付」という日本語の語感リズムで覚えてしまうのが早い。企業の経営権取得などを目的として,不特定多数の株主から株式を買い付ける手法のこと。
4Pと4Cの覚え方
それぞれの詳細は覚えると不毛なので,4Pは企業側視点,4Cは顧客側視点であることだけ押さえる。
ABC分析と相性の良いグラフ
パレート図
AIDMAモデルの覚え方
全部覚えようとすると不毛なので,最初のAはAttentionで最後のAはActionであることを押さえておけば「消費者が商品を認知してから購入に至るまでのプロセスを表すモデル」であることが理解できる。
FSPの覚え方
気合いで語源を覚えるしかない。Frequent Shoppers Programでポイント施策のイメージ。
インバウンドマーケティングのインバウンドとは
自発的な行動という意味。旅行業界のインバウンドとは意味が異なるため注意。
生活必需品の弾性力は高いか低いか
低い。価格が変動しても変わらず買い続けるから。ちなみに弾性力の定義は
価格弾性力=需要の変化率÷価格の変化率
であるから,弾性力が1の場合は価格の変化率と需要の変化率が同水準になる。
スキミングプライシングの覚え方
skimmingが「上澄み」という意味であることから,高価格でも買ってくれる市場の上層から利益をすくい取るイメージで覚えればよい。対照的な戦略はペネとレーション戦略で,中間的な戦略はバリュープライシング。
ブランドエクイティの覚え方
エクイティは資産価値という意味。ブランドの価値のこと。「Equity」を「Exploit」と混同して「ブランド活用」と誤解していたので要注意。
SECIモデルの覚え方
過去問題の出題文章をそのまま使って覚えるのが一番早い。
- 共同化(暗黙知→暗黙知)
組織内の個人,小グループで暗黙知の共有化や,新たな暗黙知の創造を行うこと - 表出化(暗黙知→形式知)
組織内の個人,小グループが有する暗黙知を形式知として明示化すること - 連結化(形式知→形式知)
明示化した形式知を組み合わせ,それを基に新たな知識を創造すること - 内面化(形式知→暗黙知)
新たに創造された知識を組織に広め,新たな暗黙知を習得すること
ベンチャー企業の関門の覚え方
小さい順に川・谷・海の3つの「溝」があると覚える。次に基礎研究・製品開発・事業化・市場定着の流れを押さえる。すると,
- 魔の川:基礎研究から製品開発への難しさ
- 死の谷:製品開発から事業化への難しさ
- ダーウィンの海:事業競争を経て市場定着させる難しさ
と覚えられる。
キャズムの覚え方
初期市場とメイン市場の溝を指す。初期市場はイノベータ・アーリーアダプター(インフルエンサー)のことを指していて,メイン市場はアーリーマジョリティ・レイトマジョリティ・ラガードを指す。マジョリティとついているのでメイン市場であることはすぐに覚えられる。ラガードは硬派なおじさんおばさんのイメージ。
事業継続マネジメントシステムを規定しているJISは何か
JIS Q 22301
IDEALの覚え方
全部覚えるのは不毛だが,PDCAサイクルと同じようにIDEALサイクルと口に馴染ませる。あとは選択肢の順番を自然に並び替えるだけ。「解決策の先行評価・試行・展開」と「改善計画の策定」の順番で悩むことがあるが,当然計画を最初に立てる。Establishingが計画,Actingが行動。先行という言葉に騙されないように。
BPRとBPOの覚え方
BPはBusiness ProcessでRはRe-engineeringでOはOutsourcingを表す。つまりBPRは既存組織やルールの根本的な見直し,BPOは外部専門業者への委託を表す。
ERPの覚え方
ERはEnterprise ResourceでPはPlanningと覚えるしかない。
SCORの覚え方
SCと見たらSupply Chainを疑う。ORはOperations Reference model。つまりSCM全体でフレームワークやビジネスプロセスを共通化することを表す。
RFI・RFQ・RFPの違い
RFはRequest Forで,IはInformation・QはQuotation・PはProposalを表す。つまり,
- RFI:ベンダーリストアップ
- RFQ:見積もり作成
- RFP:ベンダー決定&要件インプット
QはQuestionではなくQuotation(見積もり)であるため注意してください。
IRR法の覚え方
内部収益率に基づく投資効果の評価方法。投資から回収される現金収入の現在価値が投資額に等しくなるような割引率を求め,基準の割引率よりも大きければ有利と評価する方法。「今の利益ってめっちゃ割り引かないと投資額に等しくならないわ」という状況であればGoodだよねという評価軸。
CSRの覚え方
Corporate Social Responsibilityを気合いで覚えるしかない。
X理論とY理論の覚え方
Xの方がSNSアプリのアイコンのイメージから黒い印象がある。だから「人間は怠け者だ」というダークサイド。YはXの反対だから「自ら進んで責任を追う」という立場。
QC7つ道具の特性要因図と管理図の覚え方
- 特性要因図:フィッシュボーンチャートで覚える。骨の形をしたグラフ。
- 管理図:時系列データについて基準値からのブレを表現。折れ線グラフ。
新QC7つ道具のPDPC法の覚え方
正式名称を覚えてもイメージ湧かないので「目標達成までの障害と代替案を明確にする手法」と覚える。
QC7つの道具は数値データ,新QC7つの道具は数値化しにくいデータを扱うのに優れています。
EMS・OEM・ODMの覚え方
EMSは他社の電子機器の受託開発全般,OEMはその中でも製造だけを担う形態,ODMは設計から製造までを担う形態のことを指す。EMSのEはElectronics,OEMのEMはEquipment Manufacturing,ODMのDMはOriginal Design Manufacturingを表すことから覚える。
- EMS:Electronics Manufacturing Service
- OEM:Original Equipment Manufacturing
- ODM:Original Design Manufacturing
TRIZの覚え方
過去の特許や発明からアイディアを抽出する方法。ロシア語なので覚えるしかない。
HEMSの覚え方
HEMSのHEがHome Energyと押さえてしまえば住宅エネルギー管理システムであることが分かる。
損益分岐点の出し方
固定費÷(1-変動費率)の導出は簡単だが何回か使っていると覚える。
変動費率は変動費÷売上高で求められます。
実用新案権にプログラムは含まれるか
含まれない
著作権にプログラムは含まれるか
含まれる(ただしプログラム言語やアルゴリズムは「アイディア」とされるため含まれない)
プログラム言語やアルゴリズムの「アイディア」は特許権によって保護される対象です。
EDMモデルの覚え方
Evaluateで評価,Directで指示,Monitorでモニタの頭文字で経営陣がとるべき行動であると覚えるしかない。
エンタープライズアーキテクチャの4つのモデルの覚え方
モデル名はReference modelを表すRMを用いて表される。
- BRM:ビジネス。業務やシステムで共通化の対象領域を洗い出す。
- DRM:データ。情報の再利用・統合を促進するモデル。
- SDM:サービス。アプリを機能的に分類・体系化して再利用を促すモデル。
- TRM:技術。技術の標準化を促進するモデル。
EVAの求め方
Economic Value Addedなので経済的付加価値。税引後営業利益から資本費用を引くだけ。
ROEとROAの関係
ROE×自己資本比率=ROA
ゆえに自己資本比率の増加はROEを減少させる。
- ROE=当期純利益÷自己資本
- ROA=当期純利益÷総資本
であることを思い出すと,自己資本比率が高まるとROEの分母が大きくなるのでROEが小さくなる。
総資本回転率とROE・ROAの関係
総資本回転率=売上高÷総資本
単純に考えてしまうと,総資本回転率が上がると売上が上がる。するとROE・ROAの分子が大きくなるのでROEもROAも大きくなる。ROAは
ROA=当期純利益率×総資本回転率=(当期純利益÷売上高)×(売上高÷総資本)
と表される。
OC曲線と不良品の閾値の関係
「不良品がC個以下であれば合格とする」のCを小さくすればするほどOC曲線は急峻になる。
リーダーシップのコンティンジェンシー理論の覚え方
最適なスタイルは存在しないとするもの。コンティンジェンシープランのコンティンジェンシーは「不測の」という意味なので類推できるだろう。
SPAの覚え方
原義を覚えると大変なので,中間業者を排除して一気通貫で自社管理する業態のことと気合いで覚える。
ちなみにSFAはSales Force Automationで営業力の強化を表す単語です。
3PLの覚え方
3rd-Party Logisticsを押さえれば物流業務全般を請け負うアウトソーシングサービスであると理解できる。
MRPの覚え方
Material Requirements Planningを覚えるのが早い。生産計画から資材所要量を計画して発注する。
ファブレスの覚え方
ファブレスのファブはfabricationの頭文字で工場という意味。なので自社で製造工場を持たずに設計や開発に特化した企業のことを指す。例えば半導体だとQualcommが設計,TSMCが製造を請け負う。
エスクローサービスの覚え方
escrowが委託という意味であるため,委託であることに価値がある取引仲介サービスのことを指す。例えばネットオークションの出品者と落札者の取引を仲介するサービスなど。
午後I
ITストラテジストの午後Iはほぼ国語の問題なので,問題文をしっかり読んで論理構造に注意しながら回答すれば合格点を取るのは容易でしょう。
午後II
午後IIは小論文の出題であり,様々なコツが存在します。管理人が学んだことをまとめます。
大前提
ITストラテジストは筆記試験ですので,何らかの統一的な採点基準が存在します。ですから,どれだけ感動的な小論文を書いても採点基準を満たさなければ合格点はもらえません。この採点基準は公開されていませんが,重要な項目としては以下が挙げられると考えられます。
- 問いに答えているか
- ITストラテジストとしての専門性を有しているか
それぞれ簡単に見ていきましょう。
問いに答えているか
最も大切なポイントと言えます。自己満足の小論文を書かないように注意しなくてはなりません。問題文から小論文の章立てを作成する練習は必須でしょう。例えば,令和6年度の問題文から小論文の章立てを作ると以下のようになります。
- 設問ア あなたが携わったDXの実現に向けた新たな情報技術の採用について,DXの狙い,施策の内容,検討対象となった新たな情報技術とその必要性を,事業特性とともに,800字以内で述べよ。
-
- 第1章 DXの実現に向けた新たな情報技術の採用
- 1ー1 事業特性,DXの狙いと施策の内容
- 1−2 検討対象となった新たな情報技術とその必要性
- 第1章 DXの実現に向けた新たな情報技術の採用
- 設問イ 設問アで述べた新たな情報技術について,施策の実施に向けて,あなたはどのような机上確認と技術検証を行ったか,その結果や工夫したこととともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
-
- 第2章 新たな情報技術の机上確認と技術検証
- 2ー1 施策の実施に向けて行った机上確認と技術検証
- 2−2 机上確認と技術検証の結果と工夫したこと
- 第2章 新たな情報技術の机上確認と技術検証
- 設問ウ 設問イで述べた情報技術を採用するに当たって,机上確認と技術検証を通して,あなたはどのようなリスクとその対策を具体化し,経営層にどのように説明したか,経営層からの指摘,指摘を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
-
- 第3章 リスクと対策,経営層への説明と指摘,改善点
- 3ー1 具体化したリスクとその対策,経営層への説明方法
- 3−2 経営層からの指摘,指摘を受けて改善したこと
- 第3章 リスクと対策,経営層への説明と指摘,改善点
章のタイトルは,設問の日本語をそのまま引っ張ってきてもよいです。例えば,第1章の場合は「DXの実現に向けた新たな情報技術の採用について,DXの狙い,施策の内容,検討対象となった新たな情報技術とその必要性,事業特性」としてしまうのです。ただ,個人的にはこれは最後の手段にしたいと思っています。文字数稼ぎとも捉えられますし,タイトルは本来要約した内容で書かれるべきだからです。ただ,この小論文は学術的な論文ではなく,あくまでもITストラテジスト試験に合格するための小論文であるため,「問いに答えているか」を重要視すると設問の内容をそのまま章のタイトルとして利用する方針も考えられます。
ITストラテジストとしての専門性を有しているか
午後IIではITストラテジストとしての専門性を示す必要があるため,午前IIで学んだ知識を活用するとよいでしょう。ここでは,管理人が適用できそうな午前IIの知識をまとめます。
まず,バリューチェーン分析は有用です。企業活動のどこで価値が付加されているのかを分析する手法であり,内部構造は自由にいじってもよいフォーマットなので「XXするため,バリューチェーン分析を実施した」と書いておけばなんとかなるでしょう。
SWOT分析もサクッと使えて便利です。ジム経営を例に挙げてみます。以下のように強みと弱みを構造的に表現することが可能です。
| 強み | 弱み | |
|---|---|---|
| 内部環境 | 高い営業推進力 | エンジニア不足 |
| 外部環境 | 健康意識の高まり | インフルエンサーの参入 |
コストリーダーシップ戦略もサクッと使うことができます。ポーターの成長戦略では「コストリーダーシップ戦略」「差別化戦略」「ニッチ戦略」に分けられるます。差別化戦略は「高くても売れる」を意味し,ニッチ戦略はターゲットの絞り込みを意味します。よくある汎用シナリオとしては,最初はニッチ戦略からスタートし,スケールさせるためにコストリーダーシップ戦略へシフトした上で,最後に差別化戦略でアップセルを狙うというものです。
KGI・CSF・KPIも当然利用しやすいです。この際,具体的な数値も記述するようにすると効果的です。例えば,KGIとして売上50%アップ,CSFとして既存顧客の囲い込みと新規顧客の獲得,KPIとして解約率の3%ダウンと全国出店数100店舗のように設定します。ただし,デタラメな数値は用いない方が無難でしょう。
事前に考えるべきコンテキスト
本番の試験では100%真実を記述する必要はありませんが,実体験に基づく方が論理的に正しい内容を書ける可能性が高いです。そこで管理人は,自身の経験を振り返り一番深く関わった大型プロジェクトを想定シナリオとして準備しておくことにしました。各設問で問われやすい内容に対し,この大型プロジェクトのコンテキストを当てはめていく作業を行います。
| 設問 | 観点 | 内容 |
|---|---|---|
| ア | 事業概要 | A社は超大手の人材サービス会社であり,Web上で複数の人材紹介サービスを運営している。いずれのサービスも人材領域においては日本トップクラスのマーケットシェアを誇っており,求職者と採用担当者をマッチングさせることで長年人材業界を支えてきた。 |
| 事業特性 | 人材紹介サービスにおいては職業安定法を遵守する必要があり,一般的な求人公開サービスと比べて法規制が厳格であるという特性がある。A社は超大手企業であるためコスト削減意識はそこまで高くなく,新規事業に対しても背景と打ち手が合理的であれば十分な投資を行うことができる財政状況である一方で,その影響規模の大きさから経営層は法令遵守の意識が強い状態にあった。 | |
| 背景および課題 | 近年は各サービスが独立してエンハンス活動を行っており,A社としては求職者のデータを大量に保有しながらも十分に活用できていないという状況であった。各サービスが独自の構造でデータを取得しており,それぞれの対応関係が不明であるため,データを活用することが難しかったのである。 | |
| イ | 新しいビジネスモデル | A社は,求職者のデータを改めて統一的な形で取り直すプロジェクトを発足した。従来のルールベースのレコメンドではなく,データドリブンなレコメンドにより求職者と採用担当者のマッチングの精度と速度を向上させることを目指すプロジェクトである。ITストラテジストとしてこのプロジェクトに携わることになった私は,各サービス共通の求職者データ基盤として職務経歴書作成サービスを構築することにした。このサービス上では,求職者が職務経歴書のデータを入力することができると同時に,職務経歴書をPDFとしてダウンロードすることができる。 |
| 提供価値の定義 | このサービスで取得したデータを利用することにより,求職者に対して希望条件に基づくルールベースのレコメンドしかできていなかったものを,職務経歴書データのクラスタリング分析により同じクラスタからのレコメンドができるようになる。具体的には,技術営業を希望している求職者に対し,従来は技術営業関連のジョブしかレコメンドできなかったものを,同一の年収帯・職歴・学歴・スキル・資格などを保有するクラスタに属する技術営業に閉じないジョブをレコメンドできるようになった。 | |
| 工夫したこと | 取得するデータはA社共通のIDに紐づかせることで,横断的なデータの利活用を促進した。また,取得するデータを機械学習のモデルに学習させるため,スキルや資格といった情報は構造化されたペアデータとして取得した。この際,スキルや資格の構造化を10,000件以上作成する必要があったため,LLMを利用して一般的な構造でスキルや資格を体系化した。また,一般にはPDFを生成する処理は重くなることが多いため,求職者がデータを更新したタイミングでPDFを生成する非同期処理により,PDFダウンロード機能を高速化した。 | |
| ウ | 想定リスクとその対策 | 本サービスはA社内において複数の人材紹介サービスから利用される構造になるため,将来的には大量アクセスによりサーバへの負荷が高まり,利用ユーザのUXが低下する恐れがあった。そこで私は,A社内の利用サービスとサービス稼働率のSLAを握ることにした。その際,本サービスが停止している状況であっても極力利用サービスには縮退運用を続けてもらう設計を行うことにより,想定リスクの低減を図った。チーム内部ではSLOを定めることにより,そのSLOを達成できるようにサーバのプロビジョニングを行った。これにより,A社の人材紹介領域全体として安定的なサービス提供が可能になった。 |
| 経営層への説明 | 人材紹介サービスでは求職者が実際に入社することにより報酬を得るビジネスモデルを採用しているため,職務経歴書のダウンロード機能が利用できないと求職者が応募プロセスに進むことができず,収益が落ちてしまう構造になっている。そこで私は,本サービスが停止していても人材紹介サービス側が縮退運用を続けることを経営層に説明した。さらに,本サービスがSLAを遵守している限りはA社人材紹介サービスの売上の毀損が最大でも1%未満に収まることを説明し,想定リスクとその対応について納得してもらうことができた。 | |
| 評価や指摘を踏まえた改善 | 経営層からはSLAの設計については高く評価されたが,非同期でPDFを生成することによりユーザは常に最新のPDFがダウンロードできるとは限らず,職業安定法に抵触する恐れがあるのではないかと指摘を受けた。そこで私は,PDFダウンロード機能においては常に最新のPDFを生成するように仕様を変更するため,PDFダウンロードページにおいては通常のWebページよりも長いレイテンシーを許容することを新たにSLAとして利用サービスと合意し,職業安定法に抵触するリスクを最小化することに成功した。 |
設問との整合性について
上記コンテキストは本番の設問と完全に整合するとは限りません。したがって,この内容を全て書き切るというよりは,この内容をベースにして書けそうな設問を選んだ上で,「問いに答えているか」を最重要視する意識が大切です。事前に準備していた内容を切り捨てる勇気が必要です。
アンケートシート
午後IIでは小論文の題材とする企業の情報を記入する通称アンケートシートを書く必要があります。本番中に考えていたら時間がもったいないですし,そもそもテーマは事前に準備しておくものですから,アンケートシートの内容は予め埋められるようになっておきましょう。内容は100%真実を書く必要はなく,ITストラテジストとしての小論文として一番採点基準に刺しにいきやすい立場を演じるべきでしょう。
| 質問 | 記入内容 |
|---|---|
| 名称 | 職務経歴書作成サービスの構築 |
| 企業・機関などの種類・業種 | 7. サービス業 |
| 企業・機関などの規模 | 5. 5001人以上 |
| 対象業務の領域 | 6. 人事 |
| システムの形態と規模 | 2. Webシステム(サーバ約50台,クライアント分からない) |
| ネットワークの範囲 | 2. 同一企業・同一機関の複数事業所間 |
| システムの利用者数 | 7. 3001人以上 |
| 総工数 | 約300人月 |
| 総額 | 500百万円 |
| 期間 | 2022年01月〜2022年12月 |
| あなたが所属する企業・機関 | 1. ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業など |
| あなたが担当した業務 | 3. 企画 4. 要件定義 5. 設計・開発・テスト・導入 |
| あなたの役割 | 2. チームリーダー |
| あなたが参加したチームの構成人数 | 20人 |
| あなたの担当期間 | 2022年01月〜2022年12月 |

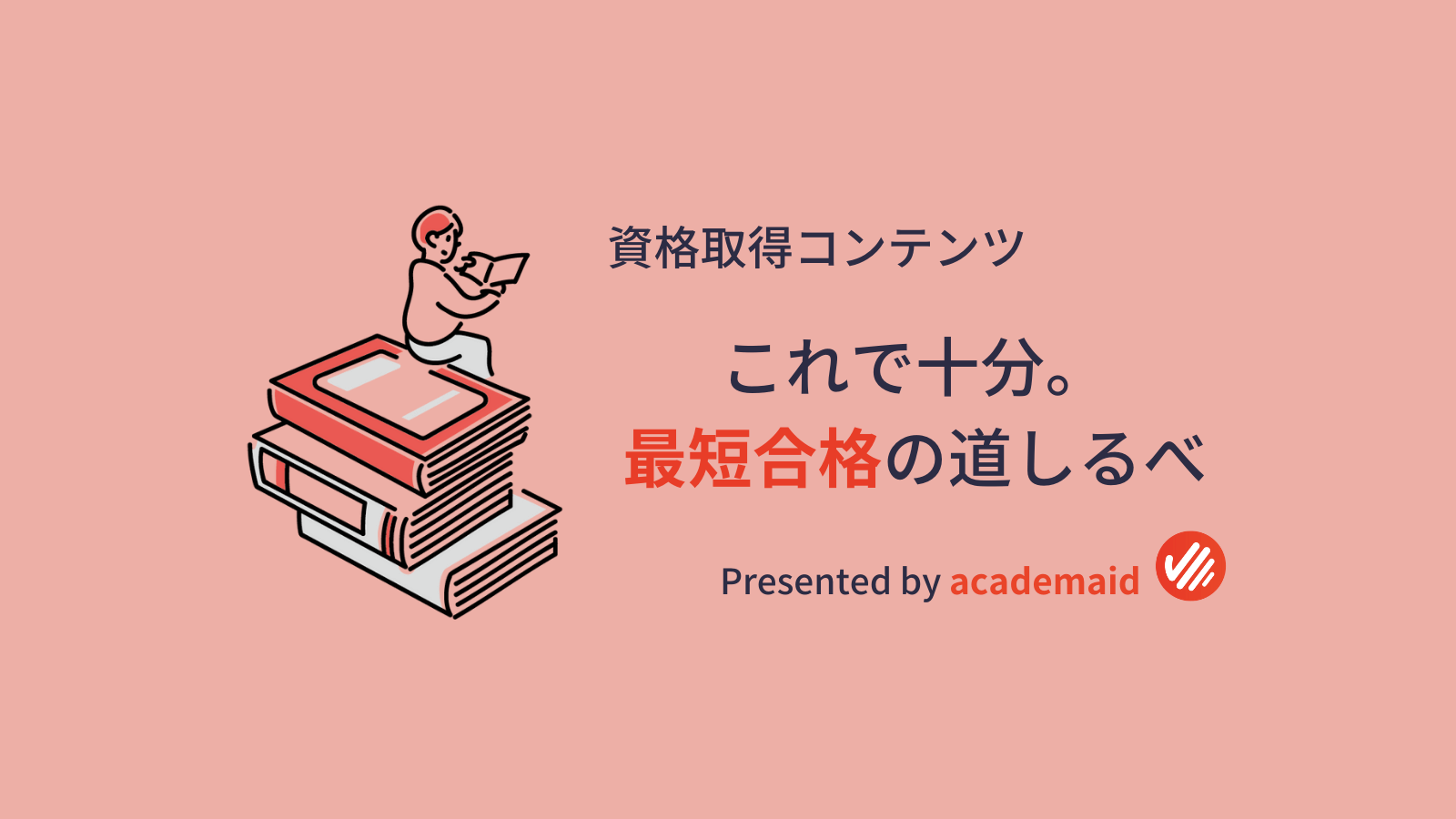
コメント