【ネスぺ対策】忘れやすいプロトコル早見表
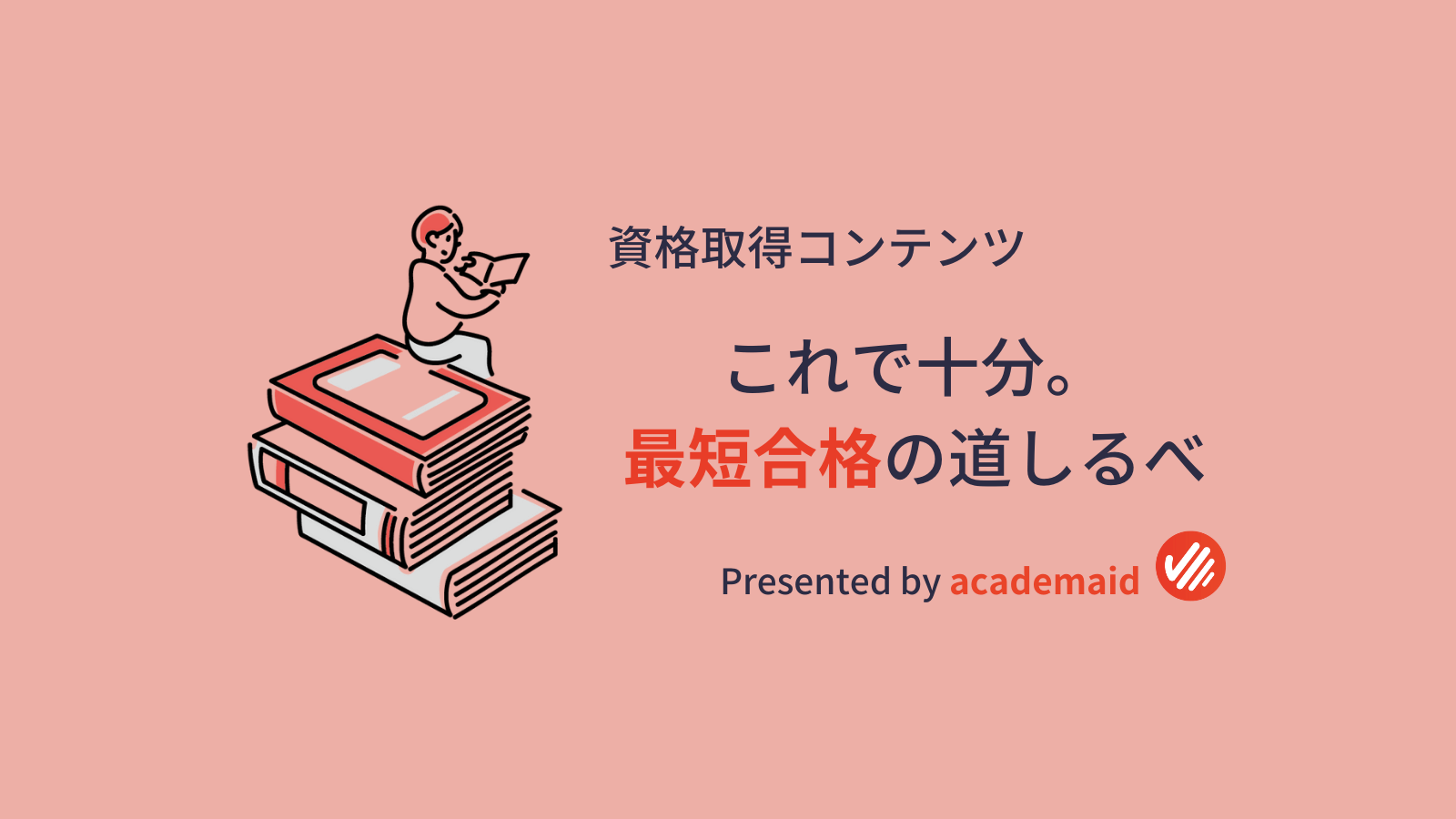
本稿ではIPA試験で必要とされる知識をまとめます。
目次
忘れやすいプロトコル早見表
本記事では,忘れやすく覚えにくいプロトコルを以下の観点でまとめていきます。
- 何の略称か
- TCP/IP階層モデルにおいて第何層に属するか
- 何を規定するプロトコルか
HDLC
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | High-level Data Link Control |
|---|
| レイヤー | ネットワークインタフェース層 |
|---|
| 説明 | 大量かつ高速な伝送制御手順。誤り制御にCRCを利用しているため信頼性の高いデータ転送が可能。キャラクタ単位で伝送するベーシック手順とは異なり,フレームと呼ばれる単位を採用して任意長のデータ伝送を可能にした。 |
|---|
PPP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Point-to-Point Protocol |
|---|
| レイヤー | ネットワークインタフェース層 |
|---|
| 説明 | 一対一で端末を接続するためのプロトコル。伝送モードは全二重方式でHDLC手順を用いる。 |
|---|
OSI参照モデルにおいてイーサネットやFDDIは物理層とデータリンク層にまたがって動作するプロトコルであるのに対し,PPPは純粋なデータリンク層で動作する点に注意する。
ICMP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Internet Control Message Protocol |
|---|
| レイヤー | インターネット層〜トラスポート層 |
|---|
| 説明 | IPプロトコルの「エラー通知」や「制御メッセージ」を転送するためのプロトコル。 |
|---|
ICMPが属するレイヤーはこちらの記事をご参照ください。
GRE
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Generic Routing Encapsulation |
|---|
| レイヤー | インターネット層 |
|---|
| 説明 | L3でトンネリングを行うためのプロトコル。マルチキャストに対応していないプロトコルをカプセル化することでマルチキャストを可能にすることができる。GRE単体では暗号化の機能を有していないため,IPsecと組み合わせて利用される。この形態はGRE over IPsecと呼ばれる。 |
|---|
OpenFlow
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | - |
|---|
| レイヤー | - |
|---|
| 説明 | TCP/IP階層モデルには属さず,物理層からアプリケーション層までを新しい枠組みで規定するプロトコル。データ転送と経路制御の機能を論理的に分離し,OpenFlowコントローラと呼ばれるソフトウェアがOpenFlowスイッチと呼ばれるネットワーク機器のデータ転送の制御と管理を行う。柔軟にネットワーク構成を管理できる状態を目指し,SDNを実現しようとするプロトコルである。 |
|---|
SMTP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Simple Mail Transfer Protocol |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | インターネットで電子メールを転送するためのプロトコル。 |
|---|
SPF
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Sender Policy Framework |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | SMTP接続してきたメールサーバのIPアドレスを参照し,正規のサーバから送られた電子メールかどうかを検証するためのプロトコル。 |
|---|
OP25B
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Outbound Port 25 Blocking |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | 内部ネットワークからTCP/25を使った外部ネットワークへの通信を遮断することにより,スパムメールなどの送信を防ぐためのプロトコル。 |
|---|
DKIM
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Domain Keys Identified Mail |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | 電子メールのディジタル署名を検証し,なりすましや改ざんを検知するためのプロトコル。 |
|---|
SNMP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Simple Network Management Protocol |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | TCP/IP上で機器の情報を収集し,監視や制御を行うためのプロトコル。UDPを用いる。 |
|---|
IGMP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Internet Group Management Protocol |
|---|
| レイヤー | インターネット層 |
|---|
| 説明 | 受信側がマルチキャストのグループに所属することを通知し,ルータがその情報を広めるためのプロトコル。UDPを用いる。 |
|---|
RTP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Real-time Transport Protocol |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | 音声や動画などをリアルタイムに配送するためのプロトコル。ほとんどがUDP上で動作するが,YoutubeなどではGoogle独自のプロトコルがTCPベースで運用されている。 |
|---|
RTCP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | RTP Control Protocol |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | パケット喪失率など通信回路の品質を管理し,RTPの補助を行うためのプロトコル。RTPのデータ転送レートなどを管理する。 |
|---|
SIP/SDP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Session Initiation(Description)Protocol |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | P2Pのリアルタイムなセッションを確立するためのHTTPをベースとしたプロトコル。SIPにおいてマルチメディアセッションの記述にはSDPを用い,マルチメディアデータの送受信はRTPを用いるという関係。 |
|---|
 SIP/SDPの構造化
SIP/SDPの構造化
NTP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Network Time Protocol |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | 時刻を同期するためのプロトコル。UDPを用いる。 |
|---|
LDAP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Lightweight Directory Access Protocol(エルダップ) |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | ユーザ名やパスワードなどの情報を一元管理する仕組みを規定するプロトコル。具体的には,処理が重いX.500シリーズのDAP(Directory Access Protocol)を軽量化してTCP/IP上で使えるようにしたものである。 |
|---|
SCTP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Stream Control Transmission Protocol |
|---|
| レイヤー | トランスポート層 |
|---|
| 説明 | TCPと同様に信頼性を担保するためのプロトコル。特徴は下記。
・アプリケーションが定めるメッセージ(チャンク)サイズ単位の送受信
・メッセージの生存時間を定義可能
・一つのホストに複数のネットワークインタフェースを設定できるマルチホーミングに対応
・無線LAN→イーサネットなど使用するNICが変わっても通信を継続可能
・TCPで複数のコネクションを確立する通信を一つのコネクションで実現 |
|---|
DCCP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Datagram Congestion Control Protocol |
|---|
| レイヤー | トランスポート層 |
|---|
| 説明 | UDPの輻輳制御をサポートするためのプロトコル。特徴は下記。
・コネクションの確立と切断がある
・確認応答を利用してパケットの再送を行うこともできる |
|---|
UDP-Light
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Lightweight User Datagram Protocol |
|---|
| レイヤー | トランスポート層 |
|---|
| 説明 | UDPのチェックサム機能の対象範囲を必要最低限に絞ることで通信効率を高めたプロトコル。名前からUDPを軽量にしたプロトコルと勘違いされがちだが,実際はUDPを拡張したプロトコルである点に注意する。 |
|---|
OCSP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Online Certificate Status Protocol |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | ディジタル証明書の失効リスト(CRL)をリアルタイムに取得するためのプロトコル。サーバ構築等の下準備が必要である点に注意する。 |
|---|
LACP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Link Aggregation Control Protocol |
|---|
| レイヤー | ネットワークインタフェース層 |
|---|
| 説明 | リンクアグリゲーションを動的に設定するためのプロトコル。 |
|---|
RMON
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Remote network MONitoring |
|---|
| レイヤー | RMON1:ネットワークインタフェース層以下
RMON2:インターネット層以上 |
|---|
| 説明 | SNMPでパケットキャプチャを管理装置に送って解析するためのプロトコル。 |
|---|
PLCP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Physical Layer Convergence Protocol |
|---|
| レイヤー | 物理層 |
|---|
| 説明 | IEEE 802.11(無線LAN)の物理層。有線LANでは同期用のプリアンブルしか定義されていなかったが,無線LANでは同期用のPLCPプリアンブルに加えてMIMOの情報を記載するPLCPヘッダが定義されている。 |
|---|
LLDP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Link Layer Discovery Protocol |
|---|
| レイヤー | ネットワークインタフェース層 |
|---|
| 説明 | 隣接する機器に自身の機器情報をアドバタイズするためのプロトコル。APとPoEスイッチ間でPoE規格や最大供給電力を交渉する際にも利用される。 |
|---|
MLD
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Multicast Listener Discovery |
|---|
| レイヤー | インターネット層 |
|---|
| 説明 | IPv6においてマルチキャストの受信者を探索するためのプロトコル。IPv4におけるIGMP。 |
|---|
VRRP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Virtual Router Redundancy Protocol |
|---|
| レイヤー | インターネット層 |
|---|
| 説明 | L3機器を冗長化するためのプロトコル。 |
|---|
TKIP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Temporal Key Integrity Protocol |
|---|
| レイヤー | ネットワークインタフェース層 |
|---|
| 説明 | アクセスポイントが認証局と連携してパスワードをセッションごとに生成するためのプロトコル。 |
|---|
NHRP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Next Hop Resolution Protocol |
|---|
| レイヤー | インターネット層 |
|---|
| 説明 | トンネル確立時に対向側のIPアドレスを動的に取得するためのプロトコル。IPsecに限らない。 |
|---|
SYSLOG
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | System Logging Protocol |
|---|
| レイヤー | インターネット層〜トランスポート層
※ SYSLOGが属するレイヤーはICMPと同様 |
|---|
| 説明 | IPネットワーク上でログメッセージを転送するためのプロトコル。 |
|---|
CoAP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Constrained Application Protocol |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | IoT向けのプロコトル。性能が限られた機器でも効率的に通信を可能にする。 |
|---|
MQTT
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Message Queuing Telemetry Transport |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | IoT向けの軽量メッセージングプロコトル。 |
|---|
ALPN
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Application-Layer Protocol Negotiation |
|---|
| レイヤー | セッション層〜アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | TLSハンドシェイク時にTCPの上位層のプロトコルをネゴシエーションするためのプロトコル。HTTP・FTP・IMAPなどが扱われる。Client HelloやServer Helloの拡張フィールドのような扱いで,上位層で使えるプロトコル一覧を送る。 |
|---|
SCIM
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | System for Cross-domain Identity Management |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | IDaaSでプロビジョニングを行うためのプロトコル。IDPとサービス間のHTTP通信を規定しており,REST形式のAPIを通じてJSONでやりとりを行う。 |
|---|
RDAP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | Registration Data Access Protocol |
|---|
| レイヤー | アプリケーション層 |
|---|
| 説明 | レジストリに登録したデータにアクセスするためのプロトコル。WHOISの後継として標準化されたもの。
・WHOIS:TCP/43でテキスト形式
・RDAP:TCP/80 or TCP/443でJSON形式 |
|---|
FHRP
| 項目 | 説明 |
|---|
| 略称 | First Hop Redundancy Protocol |
|---|
| レイヤー | インターネット層 |
|---|
| 説明 | デフォルトゲートウェイを冗長化するためのプロトコル。FHRPにはCisco社のルータで利用されるHSRP(Hot Standby Routing Protocol)がよく利用されるが,それ以外であればVRRPがよく利用される。 |
|---|
シェアはこちらからお願いします!


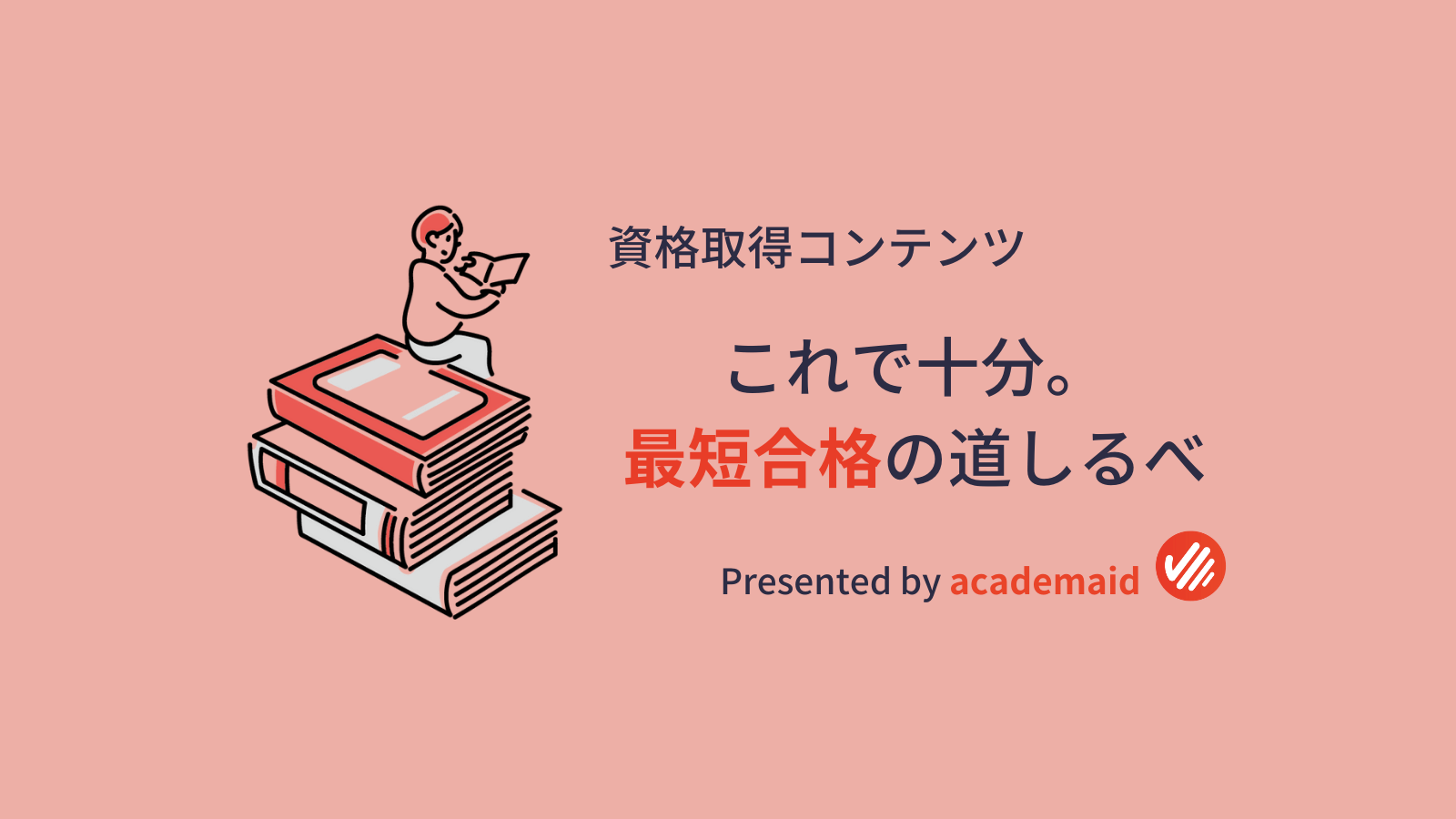
コメント