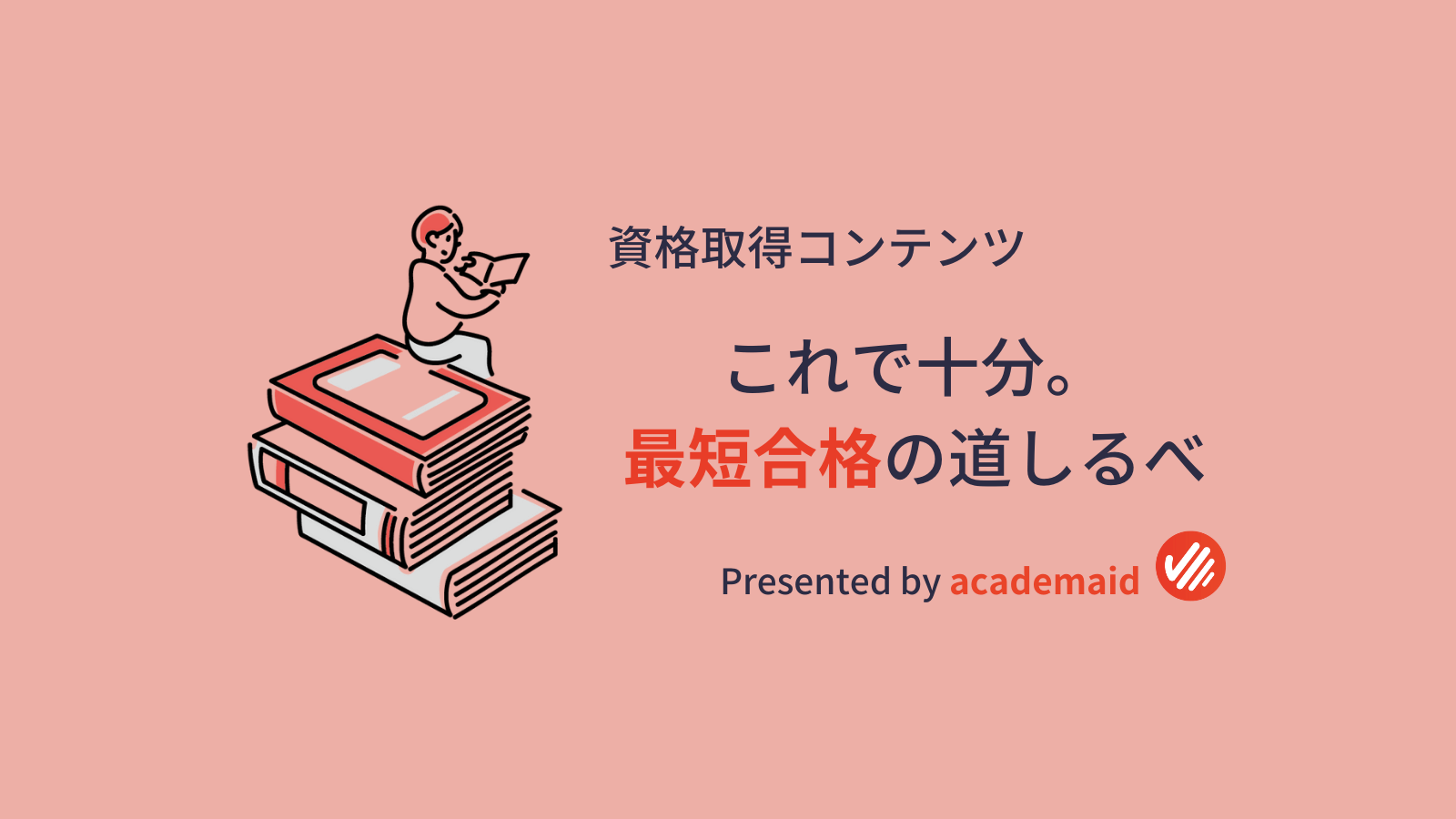本稿では日商簿記2級で必要とされる知識のうち見直すべきポイントをまとめます。
2級での論点まとめ
- 売上原価対立法
-
商品売買時の仕訳方法には三分法と売上原価対立法の2つがある。3級では三分法を学習した。これはいわゆる「しくりくりし」で,期首商品棚卸高を繰越商品から仕入に振り替えて期末商品棚卸高を仕入から繰越商品に振り替えることで売上原価を処理していた。2級では売上原価対立法を学習する。三分法とは異なり,売上時に原価を商品から振り替えてしまう方法のことを指す。
三分法
STEP仕入時借方 金額 貸方 金額 仕入 70 買掛金 70 STEP売上時借方 金額 貸方 金額 売掛金 100 売上 100 STEP決算時借方 金額 貸方 金額 仕入 60 繰越商品 60 繰越商品 80 仕入 80 売上原価対立法
STEP仕入時借方 金額 貸方 金額 商品 70 買掛金 70 STEP売上時借方 金額 貸方 金額 売掛金 100 売上 100 売上原価 50 商品 50 STEP決算時仕訳なし
両者で同じなのは売上時の売掛金/売上です。仕入時は異なるため注意してください。
- 有価証券の分類と評価
-
2級では有価証券を4つに分類し,それらを決算時に評価替えするかどうかを学ぶ。期末評価に関しては,売買を見据えた売買目的有価証券とその他有価証券は時価で評価替えする。満期保有目的有価証券は取得時の利益を償却原価法で分配する。子会社株式・関連会社株式は支配を目的とした有価証券であるため原価のままにする。
種類 期末評価 差額の処理 売買目的有価証券 時価で評価替え 有価証券評価損益 満期保有目的有価証券 償却原価法 ※ 取得時の差額が0の場合は原価 有価証券利息 子会社株式・関連会社株式 原価のまま - その他有価証券 時価で評価替え その他有価証券評価差額金 貸借対照表上では売買目的有価証券は流動資産,それ以外は固定資産として表示されます。
- サービス業の処理
-
商品における売上がサービス業では役務収益という勘定科目を用い,商品における売上原価がサービス業では役務原価という勘定科目を用いる。サービス業では「先に費用は支払ったがサービスは提供していない」という状況になり得るため,この費用は仕掛品という資産勘定科目で仕訳する。
- 税効果会計
-
会計上の利益と税法上の利益は異なる。損益計算書には税法上の利益から算出された法人税等が記載されるため,会計上の利益から算出された法人税との差額を調整する必要がある。この差額を法人税等調整額といい,このように会計と税法の違いを吸収する仕組みを税効果会計という。
- 連結会計
-
親会社と子会社の財務諸表を合算して必要な修正仕訳を行う仕組みを連結会計という。修正仕訳では内部処理を相殺したり非支配株主に対する持分を分配したりする。大元の財務諸表を修正するわけではないため,この修正仕訳自体が毎年継続的に更新されていく点が最も重要。
商業簿記
株式の発行
純資産項目を整理せよ
| 出どころ | 種類 | 科目名 |
|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 資本金:株式会社が最低限維持する金額 |
| 資本剰余金 | 資本準備金:資本金増加のうち資本金に充てなかった金額 | |
| その他資本剰余金:資本準備金以外の資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | 利益準備金:会社法で強制されている積立金 | |
| 任意積立金:会社独自の積立金 | ||
| 繰越利益剰余金:配当・処分が決定していない利益 | ||
| 評価換算差額金 | その他有価証券評価差額金:その他有価証券の時価評価により得た評価差額 | |
資本金の「会社法で認められている最低額」を説明せよ
払込金額のうち1/2
利益準備金積立額・資本準備金積立額のルールを説明せよ
財源が繰越利益剰余金の場合に「利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の1/4に達するまで,配当金の1/10を利益準備金として積み立てなければならない」というルール。財源がその他資本剰余金である場合は,利益準備金ではなく資本準備金を積み立てる。
例えば,繰越利益剰余金2,000円を株主配当金1,000円・別途積立金200円のように配分・処理することが承認されたとする。当社の資本金は4,000円・資本準備金は250円・利益準備金は50円であるときの利益準備金積立額を考える。
- 4000 * 1/4 - (250 + 50) = 700
- 1000 * 1/10 = 100
より,まだ利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の1/4に達していないことから,配当金の1/10である100円を利益準備金に積み立てる必要がある。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰越利益剰余金 | 1,300 | 未払配当金 | 1,000 |
| 別途積立金 | 200 | ||
| 利益準備金 | 100 |
商品売買
棚卸減耗損と棚卸評価損でピンとくるべき内容を説明せよ
決算整理仕訳において売上原価に含める可能性があること。棚卸減耗損と棚卸評価損は決算時に棚卸しすることによる評価差額であるため,想定される場面は決算整理仕訳。いずれも繰越商品を減らす費用として計上される。ここで商品評価損を売上原価に含める場合,単なる商品評価損という費用から仕入に振り替える必要がある。三分法では次のように仕訳する。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 棚卸減耗損 | 20 | 繰越商品 | 20 |
| 商品評価損 | 8 | 繰越商品 | 8 |
| 仕入 | 8 | 商品評価損 | 8 |
決算整理仕訳時なので「しくりくりし」の後にこれらの仕分けを行います。上二行が棚卸しの結果に帳簿を揃えるための仕訳で,最終行が商品評価損を売上原価に含めるための仕訳です。ただし,問題文で「棚卸減耗損と商品評価損は精算表上,独立の科目として表示する」と指示があった場合は,棚卸減耗損や商品評価損を仕入に振り替える必要はありません。
サービスの提供に先立って発生するお金の受け渡しに関する科目を挙げよ
- 前受金(契約負債):サービスの提供に先立って代金を受け取る
- 仕掛品:サービスの提供に先立って代金を支払う
サービス業のサービスの提供が完了した際の収益計上を説明せよ
以下のように科目を振り替える。
- 前受金(契約負債):役務収益
- 仕掛品:役務原価
例えば,イベントのチケットを¥7,000,000で現金販売し,経費として¥2,500,000を支払った場合,仕訳は次のようになる。
- イベント開催前
-
借方 金額 貸方 金額 現金 7,000 前受金 7,000 仕掛品 2,500 現金 2,500 - イベント開催後
-
借方 金額 貸方 金額 前受金 7,000 役務収益 7,000 役務原価 2,500 仕掛品 2,500
履行義務は果たしたが代金請求権がないときの勘定科目は何を使うか
契約資産
代金は請求できないのでまだ売掛金では勘定しない点に注意です。
手形
不渡手形の償還請求時に発生した費用はどの勘定科目を使うか
不渡手形に含める。償還請求費用を現金で支払った場合は次のような仕訳になる。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 不渡手形 | 110 | 受取手形 | 100 |
| 現金 | 10 |
手形を更改するときはどのような仕訳になるか
借方にも貸方にも手形の勘定科目が出てくる。利息を含める場合と含めない場合があるので注意。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 受取手形 | 110 | 受取手形 | 100 |
| 受取利息 | 10 |
思考停止で受取手形を相殺しないようにしてください。勘定科目は同じでも新手形と旧手形で異なります。
費用の支払いのために振り出した未渡小切手の決算日における仕訳方法を説明せよ
未払金で処理する
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 100 | 未払金 | 100 |
商品の掛金の場合は貸方は買掛金などになります。
固定資産
200%定率法とは何か
定額法の償却率に200%をかけた値を定率法の償却率にするルール
定額法の償却率は1/耐用年数で計算されます。例えば耐用年数10年の200%定率法の除却率は20%となります。
建物が火災で消失したときの仕訳を答えよ
火災時
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却累計額 | 600 | 建物 | 1,000 |
| 火災未決算 | 400 |
保険払込連絡時(500円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収入金 | 500 | 火災未決算 | 400 |
| 保険差益 | 100 |
補助金の仕訳方法を説明せよ
まず全額受け取ってから費用計上して相殺する。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,000 | 国庫補助金受贈益 | 1,000 |
| 備品 | 1,200 | 現金 | 1,200 |
| 固定資産圧縮損 | 1,000 | 備品 | 1,000 |
圧縮は「帳簿価格を減額すること」を意味します。上の例では備品を圧縮しています。圧縮した結果費用が計上され,その費用が補助金と相殺されるイメージです。
リース取引
リース料と見積購入価額の違いを説明せよ
- リース料:利子込み法における支払い額
- 見積購入価額:利子抜き法における支払い額
ファイナンス・リース取引では,最初にリース資産・リース債務に仕訳して債務を減らしていく。オペレーティング・リース取引では資産と債務は計上せずに,支払リース料と未払リース料を都度計上する。
有価証券
満期保有目的債権の取得時に差額益がある場合の勘定科目は何を使うか
有価証券利息を使う。例えば差額益が100円で満期まで5年ある場合は以下のようになる。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 満期保有目的債権 | 20 | 有価証券利息 | 20 |
時価法と全部純資産直入法を説明せよ
いずれも有価証券の評価替えの方式を表す。売買目的有価証券とその他有価証券にこれらを適用する仕訳問題が頻出。売買目的有価証券はその名のとおり売買が目的であり,その他有価証券も売買が目的である。したがって,両者を取得原価のまま置いておくのは不適切であり,決算時に評価替えをする必要がある。売買目的有価証券は短期的な取引も想定されるためP/Lに計上するが,その他有価証券は短期的な取引は想定されていないためP/Lに計上したくない。したがって,評価替えで現れた差異は売買目的有価証券では損益勘定を利用するが,その他有価証券では直接純資産に入れてしまう。前者を時価法,後者を全部純資産直入法という。
- 売買目的有価証券
-
短期的な取引も想定されるためP/Lに計上する。時価法。有価証券評価損益を利用する。
- その他有価証券
-
短期的な取引も想定されないためP/Lに計上しない。全部純資産直入法。ただし,直接純資産に入れてしまうと税金が無駄に徴収されてしまう。そこで,繰延税金負債とその他有価証券評価差額を利用する。繰延税金負債は税金分の負債増加分,その他有価証券評価差額は税抜き後の純資産増加分を表す。
例えば,下記のような決算を考える。
- 売買目的有価証券:3,500株・原価¥1,700・時価¥1,700
- その他有価証券:5,000株・原価¥2,200・時価¥2,500
ただし,実効税率は40%とする。この場合,仕訳は次のようになる。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 有価証券評価損益 | 700,000 | 売買目的有価証券 | 700,000 |
| その他有価証券 | 1,500,000 | 繰延税金負債 | 600,000 |
| その他有価証券評価差額金 | 900,000 |
税効果会計
税効果会計を説明せよ
税法の現金主義を会計の発生主義に寄せるための処理。「今期は損金として認められなかったが来期以降の適切なタイミングで損金になる」ようなケース(引当金繰入額など)で一時的に帳尻を合わせるための仕訳を行う。逆に,今後確実に損金として認められないことが判明しているケース(交際費の損金不算入額など)は税効果会計の範疇外となる。
税効果会計により納税額は変わりません。
法人税等調整額の対向側の勘定科目を答えよ
繰延税金資産または繰延税金負債
税効果会計は会計上の費用と法務上の損金の一時的な差異に対して適用されるものであるため,繰延税金資産は「将来税金が安くなるための資産」を表し,繰延税金負債は「将来税金を支払わなければならない負債」を表します。将来差異が解消されることが前提です。国は会計上の税金よりも多くの税金を徴収しようとするため,ほとんどの場合は借方に繰延税金資産,貸方に法人税等調整額となります。簿記二級ではその他有価証券の全部純資産直入法でプラスの評価差額が出ているケースのみ貸方に繰延税金負債を利用します。
差異が生じたときの税効果会計の仕訳を説明せよ
費用または収益の科目の逆側に法人税等調整額を記入し,対向側に繰延税金資産または繰延税金負債を記入する。金額は損金不算入額などに実効税率をかけて求める。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入 | 200 | 貸倒引当金 | 200 |
| 繰延税金資産 | 20 | 法人税等調整額 | 20 |
貸倒引当金繰入が費用の勘定科目です。
差異が解消したときの税効果会計の仕訳を説明せよ
前期で処理した調整額を元に戻す。税効果会計が一時的な差異に対して適用されるものであることを思い出す。例えば,第1期に貸倒引当金繰越に伴う20円の繰延税金資産を計上し,第2期に貸倒引当金を全額取り崩した上で32円の繰延税金資産を計上した場合は,第2期では32-20=12の繰延税金資産を計上することになる。
その他有価証券の評価替えをした場合の翌期首の仕訳を説明せよ
税効果会計の仕訳の逆仕訳を行う。例えば,評価替えの仕分けが以下だとすると,
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | 500 | その他有価証券 | 500 |
| 繰延税金資産 | 200 | その他有価証券評価差額金 | 200 |
翌期首の仕訳は以下のようになる。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 | 500 | その他有価証券評価差額金 | 500 |
| その他有価証券評価差額金 | 200 | 繰延税金資産 | 200 |
税効果会計はあくまでも決算時の一時的な帳尻合わせであると理解しましょう。
連結会計
子会社の当期純利益の修正方法を説明せよ
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 非支配株主に帰属する当期純損益 | 200 | 非支配株主持分当期変動額 | 200 |
当期純利益を直接減算するのではなく「非支配株主に帰属する当期純損益」という勘定科目を作って連結損益計算書上で減算する点がポイントです。
子会社の配当金の修正方法を説明せよ
親会社が受け取った配当金を相殺し,非支配株主持分と合わせて剰余金の配当という勘定科目に振り替える
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 受取配当金 | 180 | 剰余金の配当 | 300 |
| 非支配株主持分当期変動額 | 120 |
開始仕訳を作る際の勘定科目名のルールを説明せよ
純資産の勘定科目の後ろに「当期首残高」をつける
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金当期首残高 | 3,000 | S社株式 | 2,600 |
| 利益剰余金当期首残高 | 1,000 | 非支配株主持分当期首残高 | 1,600 |
| のれん | 200 |
ただし,連結株主資本等変動計算書を作成しない場合は「当期首残高」はつけなくてもよいです。これは逆にいえば「当期首残高」をつけるのは連結株主資本等変動計算書を作成するためということです。
利益に影響を与える項目は一律「利益剰余金当期首残高」として処理してしまう。例えば,
開始仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金当期首残高 | 3,000 | S社株式 | 2,600 |
| 利益剰余金当期首残高 | 1,000 | 非支配株主持分当期首残高 | 1,600 |
| のれん | 200 |
のれん除却
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| のれん除却 | 20 | のれん | 20 |
子会社の当期純損益振り替え
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 非支配株主に帰属する当期純損益 | 200 | 非支配株主持分当期変動額 | 200 |
子会社の配当金修正
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 受取配当金 | 180 | 剰余金の配当 | 300 |
| 非支配株主持分当期変動額 | 120 |
となる場合,のれん除却・非支配株主に帰属する当期純損益・受取配当金・剰余金の配当は利益剰余金当期首残高に変更し,非支配株主持分には連結1年目と同様に後ろに「当期首残高」をつける。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 利益剰余金当期首残高 | 20 | のれん | 20 |
| 利益剰余金当期首残高 | 160 | 非支配株主持分当期首残高 | 160 |
| 利益剰余金当期首残高 | 180 | 利益剰余金当期首残高 | 300 |
| 非支配株主持分当期首残高 | 120 |
これを開始仕訳と合わせると次のようになる。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金当期首残高 | 3,000 | S社株式 | 2,600 |
| 利益剰余金当期首残高 | 1,060 | 非支配株主持分当期首残高 | 1,640 |
| のれん | 180 |
これらの仕訳を毎回書くのは大変であるため,タイムテーブルを用いて情報を整理するとよいでしょう。
タイムテーブルを使うと何が嬉しいか
配当金の修正と当期純利益の振り替えを計算する必要がなくなり,機械的に開始仕訳を作ることができるようになること。タイムテーブルでは前期までの利益剰余金と当期初の利益剰余金が手に入るため,この差分に対して非支配株主のパーセンテージをかけることにより非支配株主持分が計算でき,開始仕訳で控除するべき金額も同時に算出されるというカラクリになっている。これは支配獲得からどれだけの期間が経過していても,前期末までをまるっと一気に計算することができるため,非常に重宝する。
| x1 3/31 | (変化分) | x3 3/31 | x4 3/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 支配割合 | 80% | 80% | 80% | |
| 資本金 | 10,000 | - | - | |
| 資本剰余金 | 5,000 | - | - | |
| 利益剰余金 | 5,000 | 2,400 600 | 8,000 | 9,000 |
| (合計) | 20,000 | 23,000 | 24,000 | |
| 非支配持分 | 4,000 | 4,600 | ||
| 支配持分 | 16,000 | - | - | |
| 取得価格 | 17,000 | - | - | |
| のれん | 1,000 | 800 |
このテーブルを元にx4 3/31の開始仕訳を書くと次のようになる。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金当期首残高 | 10,000 | S社株式 | 17,000 |
| 資本剰余金当期首残高 | 5,000 | 非支配株主持分当期首残高 | 4,600 |
| 利益剰余金当期首残高 | 5,800 ※8000としないように注意 | ||
| のれん | 800 |
利益剰余金当期首残高が8,000とならないのは,非支配株主持分も合わせた額になっているためです。
未実現利益の消去を説明せよ
親会社・子会社間で商品の売買が生じた際の修正仕訳のこと。商品の原価自体は変わらないが,本来計上するべきではない利益が計上されてしまっているため,この利益だけを修正仕訳する必要がある。例えば利益率10%の商品1,100円を親会社から子会社へ販売した場合,100円の利益は本来計上するべきではないため,商品を100円減額して売上原価を100円増額する必要がある。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上原価 | 100 | 商品 | 100 |
アップストリームの場合は以下の仕訳を加えて非支配株主にも未実現利益の消去を負担させる。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 非支配株主持分当期変動額 | 40 | 非支配株主に帰属する当期純損益 | 40 |
製造業会計
材料の棚卸減耗損はどのように扱えばよいか
一旦棚卸減耗損に振り替えてから最終的には製造間接費に振り替える
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 棚卸減耗損 | 100 | 材料 | 100 |
| 製造間接費 | 100 | 棚卸減耗損 | 100 |
この「一旦何かを経由して製造間接費に振り替える」という構造は他にも見られます。例えば減価償却費も一旦計上してから最終的に製造間接費に振り替えます。
たまった製造間接費は最終的にはどのように扱われるか
仕掛品および製造間接費配賦差異に配賦され,仕掛品は製品に振り替えられた後に売上時に売上原価に振り替えられ,製造間接費配賦差異は直接売上原価に振り替えられる。
- 製造間接費→仕掛品→(完成)→製品→(売上)→売上原価
- 製造間接費→製造間接費配賦差異→売上原価
工業簿記
材料費
材料価格差異の借方/貸方と不利/有利を対応付けよ
- 材料価格差異が借方:不利差異
- 材料価格差異が貸方:有利差異
材料価格差異が借方ということは,材料が貸方。材料が貸方ということは,予定消費額で減らした材料が減らし足りなかったということ。したがって「本来予定していた材料費より多くなってしまった」ということで会社としては嬉しくない状況なので不利差異。
材料価格差異が貸方ということは,材料が借方。材料が借方ということは,予定消費額で減らした材料が減らしすぎたということ。したがって「本来予定していた材料費より少なく済んだ」ということで会社としては嬉しい状況なので有利差異。
材料価格差異は最終的に売上原価に振り替えるため,材料価格差異が借方の場合は購入原価も借方になり費用の増加で嬉しくない,材料価格差異が貸方の場合は購入原価も貸方になり費用の現象で嬉しいということで,辻褄が合います。なお,賃料差異や製造間接費配賦差異についても同様の考え方が適用できます。
材料副費とは何か
材料の購入から出庫までにかかった付随費用のこと。予定配賦率を使って材料の購入原価に含める。例えば材料の購入代価が100円,予定配賦率が10%の場合,次のような仕訳になる。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 材料 | 120 | 現金 | 100 |
| 材料副費 | 10 |
材料副費は発生時に費用として借方に記帳されています。この材料副費を材料に配賦するのが予定配賦ですので,予定配賦時の仕訳では材料副費は貸方に記載します。「材料を増やすものが材料副費」という覚え方でもよいでしょう。
総合原価計算
複数の工程に分けられる場合の総合原価計算方法を説明せよ
後工程で「前工程費」のブロック図を加え,前工程のブロック図で計算された完成品原価を後工程のブロック図において当月投入として扱う。なお,第1工程の前工程費は直接材料費となります。
仕損品が加工進捗度よりも後・前で総合原価計算にどのような違いがそれぞれ生じるか
- 加工進捗度よりも後:ボックス図は仕損品の個数があるものとし,完成品単位原価の分母からのみ除く
- 加工進捗度よりも前:ボックス図は仕損品の個数がないものとし,平均単価計算から除く
完成品単位原価の分母からのみ除く場合,直接材料費や加工費の平均単価は仕損品のためにも費やされたとして計算されるため,単価は下がります。それゆえ,仕損品の影響は完成品にしわ寄せ(=負担)されます。一方,平均単価計算から除く場合,つまり直接材料費や加工費の平均単価は仕損品のためには費やされないものとして計算されるため,単価は上がり。それゆえ,仕損品の影響は当月投入分から負担され,結果として月末仕掛品にもしわ寄せされます。これらを言い換えると,加工進捗度よりも後の場合は完成品のみ負担,加工進捗度よりも前の場合は両者負担となります。
本社工場会計
工場が本社の得意先に直接製品を売り上げたときの処理
完成した製品を一旦本社に納入し,本社から得意先に売り上げたとして処理する。
本社
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 製品 | 100 | 工場 | 100 |
| 売掛金 | 150 | 売上 | 150 |
| 売上原価 | 100 | 製品 | 100 |
工場
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 本社 | 100 | 製品 | 100 |
標準原価計算
価格差異と数量差異はどちらを混合差異に含めるか
価格差異。混合差異にはアンコントローラブルな要素を含める。材料の価格は外部要因が多くを占めるため混合差異に含め,数量差異には混合差異を含めずに純粋な数量差異として分析した方が有意義と考える。ブロック図で考えると「価格差異をぶち抜く」と覚える。
同様に賃料と作業時間については賃料側をぶち抜きます。
販売価格差異と販売数量差異はどちらを混合差異に含めるか
販売数量差異。混合差異にはアンコントローラブルな要素を含める。販売数量は外部要因が多くを占めるため混合差異に含め,販売価格差異には混合差異を含めずに純粋な販売価格差異として分析した方が有意義と考える。ブロック図で考えると「販売数量差異をぶち抜く」と覚える。
価格差異・数量差異とは異なるため注意です。
標準操業度と基準操業度の違いを説明せよ
- 基準操業度:その月の予算の作業時間
- 標準操業度:その月に実際に完成した製品数を作るのに必要な理想作業時間
標準操業度は実際操業度があってこその概念であると理解します。
パーシャルプランとシングルプランを説明せよ
| 種類 | 仕掛品の当月投入費用 | 原価差異 |
|---|---|---|
| パーシャルプラン | 実際原価 | 仕掛品勘定 |
| シングルプラン | 標準原価 | 各原価要素の勘定(材料・賃金・製造間接費など) |
直接原価計算
固定費調整を説明せよ
直接原価計算の営業利益を全部原価計算の営業利益に一致させるための調整。一般に,直接原価計算では当期に発生した固定費を全額計上するが,全部原価計算では当期販売分だけを計上する。つまり直接原価計算の固定費は全部原価計算の固定費よりも期末製品分だけ少なくなる。この差分を埋めるのが固定費調整である。
日本語的に全部原価計算の方が固定費が多く含まれていそうですが,直接原価計算の方が多く含まれている点に注意です。「全部原価計算は販売量に応じて固定費も増減している。だから売れ残りがあればその分だけ全部原価計算の方が営業利益が高くなる」と理解する。「全部原価計算は売れ残りに対しても固定費を配賦する贅沢な計算方法だ」という理解もGood。
安全余裕率とは何か
予想売上高が損益分岐点をどの程度上回っているかを表す比率で,
(予想売上高 - 損益分岐点の売上高)/予想売上高×100
で計算できる。
経営レバレッジ係数とは何か
固定費の利用割合を示す値で,
貢献利益/営業利益
で計算できる。
問題演習
商業簿記
裏書譲渡した約束手形200円で支払人が拒絶したため請求費20円と利息10円を小切手で振り出した
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 不渡手形 | 230 | 当座預金 | 230 |
買掛金500円を支払うために作成した小切手が見渡しであった
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 500 | 買掛金 | 500 |
広告費500円を支払うために作成した小切手が見渡しであった
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 500 | 未払金 | 500 |
備品4,800円を月々832円の6ヶ月分割払いで購入し,利息を前払いした。第1回目は現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 備品 | 4,800 | 未払金 | 4,992 |
| 前払利息 | 192 | ||
| 未払金 | 832 | 現金 | 832 |
| 支払利息 | 32 | 前払利息 | 32 |
固定資産の除却時に処分価値がある場合はどの勘定科目が使われるか
貯蔵品。除却というのは「業務用として使うのをやめること」
リース料支払日と決算日が異なる場合の決算日の仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 500 | 未払利息 | 500 |
当期に支払った利息分を借方に計上し,実際にはまだリース料は支払っていないため未払利息を貸方に計上しています。
代金の法的請求権がない場合は仕訳は行うか
行う。契約資産を利用する。逆に,保守サービスなど代金を先んじて受け取る場合は契約負債を利用する。
S社に対する売り上げを相殺するための仕訳を述べよ
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上 | XXX | 売上原価 | XXX |
S社はP社に対して満期日が3ヶ月後の約束手形20,000円を振り出し,P社は手形を割り引いた
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手形 | 20,000 | 短期借入金 | 20,000 |
支払手形の振り替えと捉えましょう。
工場建物の減価償却費1,000円を計上した
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 間接製造費 | 1,000 | 減価償却費累計額 | 1,000 |
材料2,000円を外注先の工場に無償提供した
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕掛品 | 2,000 | 材料 | 2,000 |
加工品受取時に外注加工賃を間接製造費として計上します。支払いは買掛金や現金等です。
全部原価計算と直接原価計算ではどちらの方が製品有高が多いか
全部原価計算の方が多い。製品有高とは期末製品の金額のことを指すため,固定製造原価を期末製品に配賦する全部原価計算の方が製品有高が高くなる。
未収収益の勘定科目は何か
資産。逆に未払費用は負債。
払込金を資本金に充当し,別段預金を当座預金に預け替えた
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | XX | 別段預金 | XX |
| 株式申込証拠金 | XX | 資本金 | XX |
| 資本準備金 | XX |
別段預金と株式申込証拠金をそれぞれ振り替えていると読みましょう。
引っかかりポイント
- 割賦金の支払い時における利息の処理について
-
二重計上のように見える仕訳だが,負債の処理と費用の振り替えをしているため注意する。
購入時
借方 金額 貸方 金額 備品 6,000 未払金 6,240 前払利息 240 支払時(6ヶ月分割)
借方 金額 貸方 金額 未払金 1,040 当座預金 1,040 支払利息 40 前払利息 40 - 経費の消費の仕訳で経費の勘定科目がない場合
-
直接仕掛品や製造間接費に計上する
借方 金額 貸方 金額 仕掛品 800 現金 800 製造間接費 200 減価償却累計額 200 - ボックス図でどちらの軸を混合差異に含めるかという観点まとめ
-
- 棚卸減耗損と商品評価損:「棚卸高は原価で計算する」と覚える
- 価格差異と数量差異:「価格差異は実際消費量で計算する」と覚える
- 賃料と作業時間:「賃料差異は実際直接作業時間で計算する」と覚える
- 販売価格差異と販売数量差異:「販売価格差異は実績販売数量で計算する」と覚える
これらを押さえた上で,
- 商品棚卸高:実数量・時価を内側,原価・帳簿を外側
- 直接材料費および直接労務費:標準を内側,実際を外側
にする。上の覚え方では外側に置いた価格で計算するようにしているため,結果として商品棚卸高では棚卸高を混合差異に含めるためにぶち抜き,直接材料費および直接労務費では価格差異および賃料差異側を混合差異に含めるためにぶち抜くということになる。
予定と実績の大小によりぶち抜く軸が変わるということです。また,差異分析では内側から外側を引きます。
- 減価償却で残存価値を考慮する償却方法
-
- 定額法:考慮する
- 定率法:考慮しない
- 生産高比例法:考慮する
- 固定資産の買換えに関する問題
-
旧資産の売却と新資産の売却の仕訳を別で書いてマージするのが正確
- リース料の仕訳
-
ファイナンス・リース取引(利子込み法)
いつ 借方 金額 貸方 金額 リース契約日 リース資産 XXX リース債務 XXX 決算日 減価償却費 XXX 減価償却累計額 XXX 決算日翌日 - - - - リース料支払日 リース債務 XXX 現金 XXX ファイナンス・リース取引(利子抜き法)
いつ 借方 金額 貸方 金額 リース契約日 リース資産 XXX リース債務 XXX 決算日 減価償却費
支払利息XXX
XXX減価償却累計額
未払利息XXX
XXX決算日翌日 未払利息 XXX 支払利息 XXX リース料支払日 リース債務
支払利息XXX
XXX現金 XXX オペレーティング・リース取引
いつ 借方 金額 貸方 金額 リース契約日 - - - - 決算日 支払リース料 XXX 未払リース料 XXX 決算日翌日 未払リース料 XXX 支払リース料 XXX リース料支払日 支払リース料 XXX 現金 XXX - 前期に取得したソフトウェアの減価償却
-
前期の期首に取得したソフトウェアの帳簿価格は80,000円で,利用可能期間5年で償却している場合の減価償却額は,前期の減価償却を適用した結果が80,000円なので残りの利用期間4年で割ると以下が得られる。ソフトウェアは直接的な減価償却である点に十分注意する。
借方 金額 貸方 金額 ソフトウェア減価償却 1,040 ソフトウェア 1,040 - 有価証券の平均株価
-
分子には売買手数料を含めた株価を利用しなくてはならない
- 1ドル105円で仕入れた商品10ドルが期末商品棚卸高に含まれるが,決算時は1ドル110円である
-
仕訳はなにもしない。通貨・手形・売掛金・買掛金などは評価替えするが,棚卸資産・前払金などは評価替えしない。
- 「毎年同額を向こう1年分支払っている」への反応
-
前期の先払い分が含まれているという思考。例えば支払い月が7月の場合は3ヶ月を先払いしているので,今期の先払い計上分を計算する際の分母は12+3=15ヶ月となる。
- S社発行株式のXX%を取得したときのS社の純資産の扱い
-
100%でなくても純資産の100%を振り替える。例えば以下のような仕訳になる。
借方 金額 貸方 金額 資本金 8,000 S社株式 6,000 利益剰余金 2,000 非株主持分 4,000 - 利益率と利益の付加について
-
1,200円の期末商品に対して
- 20%の利益率:240円が利益分となる
- 20%の利益を付加して:200円が利益となる
- 手数料と内部副費が材料に与える影響
-
材料の原価に参入するが,結果として材料の単価が上がる。材料を仕掛品や間接製造費に振り替える際の単価が手数料と内部副費分高くなるため注意する。
- 前月未払額と当月未払額について
-
- 前月未払額:前月に計上したが実際に支払っていない賃金
- 当月未払額:当月に計上したが実際に支払っていない賃金
例えば賃金は20日締めだが原価計算期間は月末締めである場合に,7月の賃金支給額は800円,前月の未払額は30円,当月の未払額は40円の場合,仕訳は以下のようになる。
いつ 借方 金額 貸方 金額 月初の再振替 未払賃金 30 賃金 30 賃金支給 賃金 800 現金など 800 月末の未払計上 賃金 40 未払賃金 40 当月消費額は-30+800+40=810円となります。
- 賃金の実際消費量が予定消費量を超えた場合の仕訳で賃金は借方と貸方のどちらか
-
貸方。賃金を借方に計上するのは支払時。予定消費量の計上では借方の賃金を仕掛品と製造間接費に振り替える。したがって,実際消費量が予定消費量を超えた場合は借方の賃金の振り替えが足りなかったということになるため,貸方に賃金を配置して借方の賃金を仕掛品と製造間接費に振り替える。
- ボックス図と標準原価計算
-
標準原価計算ではボックス図の左側に着目し,どの時点で分析対象が投入されるかに注意する。例えば
- 分析対象:直接材料費差異
- 標準消費量:@10円×10kg
- 月初仕掛品:50個(20%)
- 当月投入:300個
- 月末仕掛品:100(50%)
- 完成品:250個
- 投入タイミング:直接材料はすべて工程の始点
- 実際直接材料費:@11円×3100kg
の場合,ボックス図の左側の当月投入は3000kgになるため,
- 価格差異:
(10 - 11) × 3100 = -3100(不利差異) - 数量差異:
(3000 - 3100) × 10 = -1000(不利差異)
となる。一方,
- 分析対象:直接労務費差異
- 標準消費量:@30円×5時間
- 月初仕掛品:50個(20%)
- 当月投入:300個
- 月末仕掛品:100(50%)
- 完成品:250個
- 投入タイミング:直接材料はすべて工程の始点
- 実際直接材料費:@28円×1,400時間
の場合,ボックス図の左側の月初仕掛品は10個,右側の月末仕掛品は50個で完成品は250個となるため,左側の当月投入は290個となる。したがって,
- 価格差異:
(30 - 28) × 1400 = 2800(有利差異) - 賃金差異:
(1450 - 1400) × 30 = 1500(有利差異)
となる。
労務費は進捗度に応じて当月投入を計算する必要があります。
- パーシャルプランとシングルプランの仕掛品勘定でピンとくるべき事項
-
パーシャルプランでは仕掛品勘定で原価差異が計上されるが,シングルプランでは計上されない点。
シングルプランでは製造費(直接材料費・直接労務費・製造間接費)勘定で原価差異が計上されます。
- 全部原価計算と直接原価計算でピンとくるべき事項
-
固定製造費の扱い。
- 全部原価計算:1個あたりの固定製造原価に販売数量を掛けた金額が売上原価
- 直接原価計算:発生額が売上原価
例えば当期生産が600個で45,000円,当期販売が550個,期末製品が50個の場合,
- 全部原価計算:
45,000 / 600 × 550 = 41,250円 - 直接原価計算:
45,000円
のようになる。
当期生産がボックス図の左下,当期販売が右上,期末製品が左下です。全部原価計算では固定製造原価を期末製品に配賦するということです。
- 検収と返品について
-
「検収基準により認識し」の場合,商品の検収終了をもって記帳する。したがって検収により不良品が見つかった場合は不良品を除いた個数で記帳する。
- 第一問の記帳対象について
-
「…が,本日,」という接続後の場合,本日より前の文章は記帳済みであり後の文章が記帳対象になる。
- 第一問の事業譲渡について
-
資産科目と負債科目はそのまま計上。純資産科目は譲渡価格と相殺し,差額をのれんとして計上する。
- 第一問の問題文で「サービス」という文字列がある場合
-
前受金・役務収益と仕掛品・役務原価を必ず疑うこと
- 減損の扱い
-
- 完成品に含める場合:最後まで個数はあるものとして計算し,最後の1個あたりの原価で個数を減損させる
- 始点から含める場合:問題文で与えられた減損額をボックス図の左側で予め減算しておく
特に始点から含める場合,ボックス図の右側を求める際は当月投入分の個数を求める際に
完成品(右側) - 月初(左側) + 月末(右側)を分母にするということは身体で覚えてしまうとよい。
- 直接材料費・加工費・直接労務費・製造間接費の関係
-
直接材料費以外は全て加工費。したがって
加工費 = 直接労務費 + 製造間接費となる。
- 支払い手形の種類
-
固定資産購入のために振り出した手形は営業外支払手形である。
- ソフトウェアや特許権の減価償却引っかけポイント
-
「前期首に取得した」場合はすでに1年分の減価償却が完了している。
- 「XX差異勘定」の覚え方
-
XXとXX差異をペアで記帳する。帳尻を合わせたい方にXXを置き,反対側にXX差異を置く。
XX差異が借方の場合は不利差異のイメージを持つとよいでしょう。
- 債権購入時の経過利息
-
来年1年分の利息をもらうのだから,購入する以前の期間に対する利息は前もって収益の逆勘定してしまうということ。
- 調整仕訳が問題文にある場合に惑わされないように
-
1株1,200円で取得し,前期末の時価は1株1,500円で,今期1株1,800円で売却したとする。この場合は1株1,200円の株式を1株1,800円で売却したと考える。前期末の評価はあくまでも決算時に調整仕訳するだけなので無視。
- 「各製造指示書に予定配賦する」が表す仕訳とは
-
製造間接費を仕掛品に振り替えるということ
- 公社債の利息に関する勘定科目
-
通貨代用証券なので現金で受け取る
- 「商品評価損は売上原価の内訳科目として処理する」とは
-
商品評価損は仕入に振り替えるということ
- 定期預金という表示科目の振り替え
-
1年を超える定期預金は決算時に長期性預金に振り替える(リース債務も同様)
- 現金預金という科目
-
現金と当座預金の合計
- 「税効果会計の処理を行う」の意味
-
片方に繰延税金資産(負債),もう片方に法人税等調整額を記帳すること。
例えば損金不算入の場合は,将来支払う税金が安くなることから繰延税金資産を借方に記帳します。
- 仕損と減損の違い
-
- 仕損:仕損品として形が残る
- 減損:形は残らない
- 工業簿記の貸借対照表
-
材料・仕掛品・製品の期末在庫(貸方)を流動資産(借方)として振り替える
- 予定単価と標準単価の違い
-
- 予定単価:過去の実績から算定した予測値
- 標準単価:無駄を省いた理想の目標値
- 配当可能な純資産科目といえば何を思い浮かべるか
-
繰越利益剰余金
- 商品評価損と棚卸減耗損はどちらを売上原価に含めるか
-
基本は商品評価損。棚卸減耗損は指定があったときのみ。ゆえに基本は商品評価損のみを仕入に振り替える。
問題によっては商品評価損も棚卸減耗損も仕入に含めない場合もあるため注意しましょう。
- クレジット手数料は税抜価格に課されるか,税込み価格に課されるか
-
税抜価格
- 満期保有目的債権を償却する際の勘定科目は何か
-
満期保有目的債権のペアは有価証券利息となる
- 税効果会計の2パターンをまとめよ
-
法人税の調整(税率40%)
借方 金額 貸方 金額 貸倒引当金繰入 X 貸倒金引当 X 繰延税金資産 0.4X 法人税等調整額 0.4X その他有価証券の評価差額(税率40%)
借方 金額 貸方 金額 その他有価証券差額金 0.6X その他有価証券 X 繰延税金資産 0.4X - 減損を始点から含める場合のボックス図の使い方
-
月初仕掛品の個数は分からなくてもよい。平均法でも右半分のうち仕掛品を除いた部分の個数で割る。
- 有価証券の切放法と洗替法の説明と仕訳
-
- 切放法:簿価自体を変更していく
- 洗替法:取得原価に戻すために期首に再振替した上で取得原価からの差分を考える
切放法
時期 借方 金額 貸方 金額 期末 売買目的有価証券 X 有価証券評価損益 X 期末 有価証券評価損益 X 損益 X 切放法
時期 借方 金額 貸方 金額 期末 売買目的有価証券 X 有価証券評価損益 X 期首 有価証券評価損益 X 売買目的有価証券 X 来期末 取得時との差分を考えればよい 取得時との差分を考えればよい - 棚卸高のボックス図で原価の方が正味売却額よりも大きく矛盾が生じた場合は何が起きるか
-
商品評価損は定義されない
- 棚卸高のボックス図で実地数量の方が帳簿価格よりも多く矛盾が生じた場合は何が起きるか
-
そんな場面は起こらず,起きたとしても訂正仕訳という違う問題になる
- 棚卸高のボックス図で「しくりくりし」の二行目の繰越商品に該当する部分はどこか
-
全体の長方形。これがP/L上の期末商品棚卸高に相当する。逆に,棚卸減耗損と商品評価損をマイナスした内側の長方形はB/S上の期末商品棚卸高になる。費用を計上する前の期末商品棚卸高が外側,費用を計上した後の期末商品棚卸高が内側になる。
- 200%定率法でよくやるミス
-
200/耐用年数で掛ける値を求めてそのまま掛けてしまう。しっかり減価償却累計額を引いてから掛けなくてはならない。圧縮されていた場合は圧縮分も引いてから掛けなくてはならない。
- 月初有高・当月仕入高・月末有高と前月未払高・当月支払高・当月未払高の違い
-
- 月初有高・当月仕入高・月末有高:
月初有高 + 当月仕入高 - 月末有高 = 当月消費額 - 前月未払高・当月支払高・当月未払高:
当月支払高 + 当月未払高 - 前月未払高 = 当月消費額
「未払」でない場合は素直なボックス図で,「未払」の場合は反対になるイメージです。
- 月初有高・当月仕入高・月末有高:
- 賃金と給料の違いを一言で説明せよ
-
- 賃金:工員に対して支払われる報酬
- 給料:工員以外に対して支払われる報酬
- 満期保有目的債権の経過利息の勘定科目は何か
-
有価証券利息
- 非支配株主に帰属する当期純利益の理解
-
科目としては収益と費用の差であり,費用の勘定科目のようなイメージ。
- 当期純利益は損益勘定を通じて繰越利益剰余金に振り替えられる
- 非支配株主に帰属する当期純利益は損益勘定を通じて非支配株主持分に振り替えられる
は対応関係にあると理解する。
- 当期純利益は費用の科目なのになぜ繰越利益剰余金に振り替えられるのか
-
費用と収益をそれぞれ同一の損益という科目に振り替えると借方に損益,貸方に繰越利益剰余金を記入することができて辻褄が合う。一方,当期純利益という用語は収益から費用を引いた値のことを指すと理解する。つまり,当期純利益を振り返るのではなく,単に差のことを当期純利益と呼んでいるだけと理解するのがよい。
- 保証率と改定償却率
-
減価償却費が未償却残高に保証率をかけた値を下回ってしまった場合,その時点での未償却残高に改定償却率を掛けた値による定額法を採用するというシステム。定率法だと延々と減価償却が終わらないため,ある閾値を設けてそれ以降は定額法に切り替えようという話。
- 本支店会計の損益勘定を説明せよ
-
本店の損益勘定は総合損益を利用し,支店はそのまま損益勘定を利用する。当期純利益がプラスの場合は損益勘定は借方に計上されることに注意すると,本店における総合損益への振替は以下のようになる。
本店
借方 金額 貸方 金額 損益 X 総合損益 X 支店の損益を本店に振り替える仕訳は以下の通り。
支店
借方 金額 貸方 金額 損益 X 本店 X 本店
借方 金額 貸方 金額 支店 X 総合損益 X - 手形関連の勘定科目注意点
-
営業に関わらない内容であれば「営業外」を付けること
- 「株式を募集するために支払った広告宣伝費」
-
株式交付費となる
- 「株式の5%を所有していたが,25%を追加購入した」
-
その他有価証券から関連会社株式に振り替える必要がある
- 発行株式の20%未満:その他有価証券
- 発行株式の20%以上50%以下:関連会社株式
- 発行株式の50%超:子会社株式
- 債務保証時の仕分けを述べよ
-
借方 金額 貸方 金額 保証債務見返 X 保証債務 X これより,取引先の債務を肩代わりした際には以下のような仕訳が発生する。
借方 金額 貸方 金額 立替金 X 当座預金 X 保証債務 X 保証債務見返 X - 小切手と手形
-
読み間違えるな。他人振り出しの小切手は現金。三級範囲。
- リース利息の分割単位
-
全期間を分母にもってくること。1年ではない。
- 「通常の出庫票により出庫記録を行った」
-
外注行者への無償支給と考える。材料を仕掛品に直接振り替える。